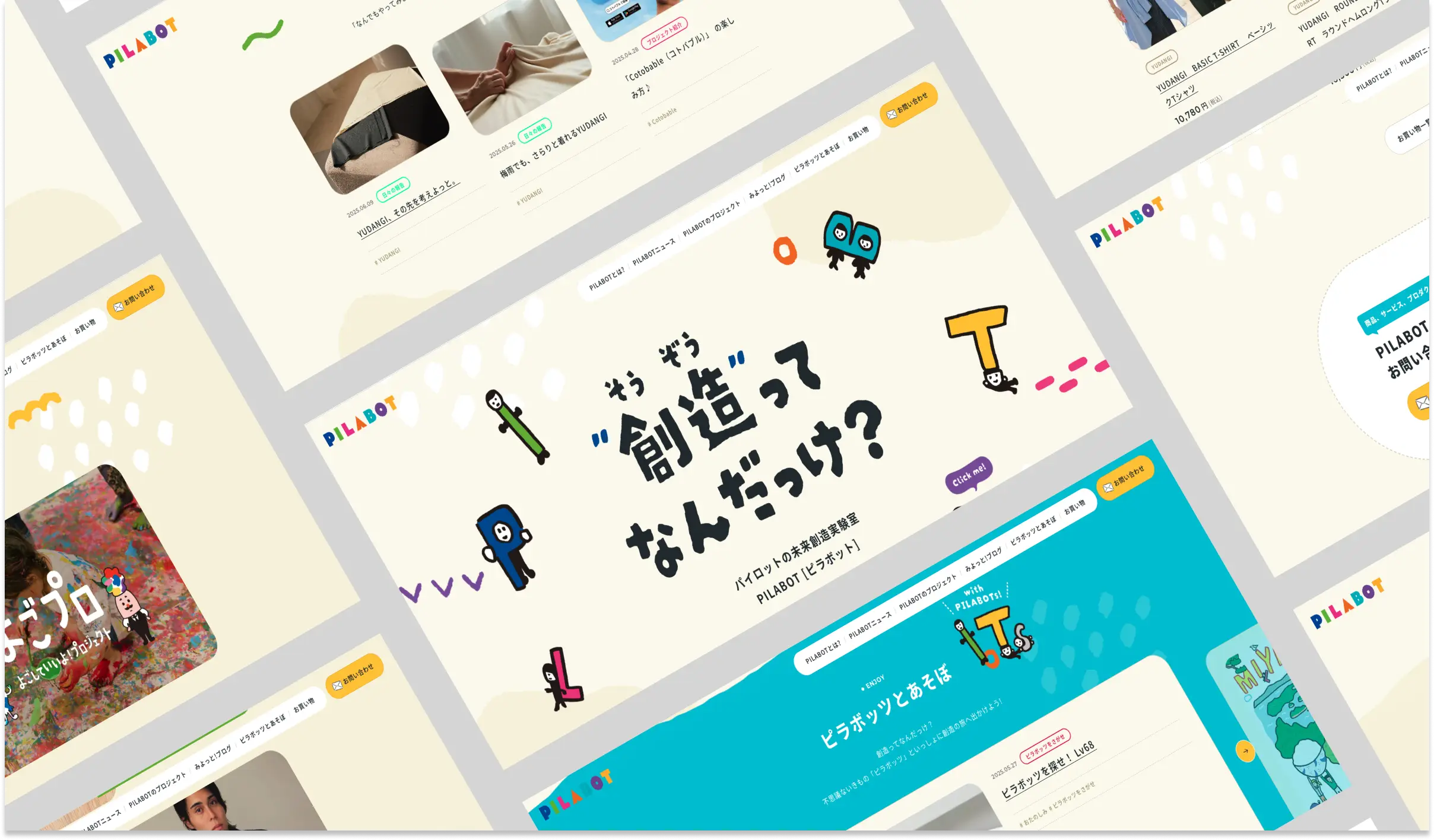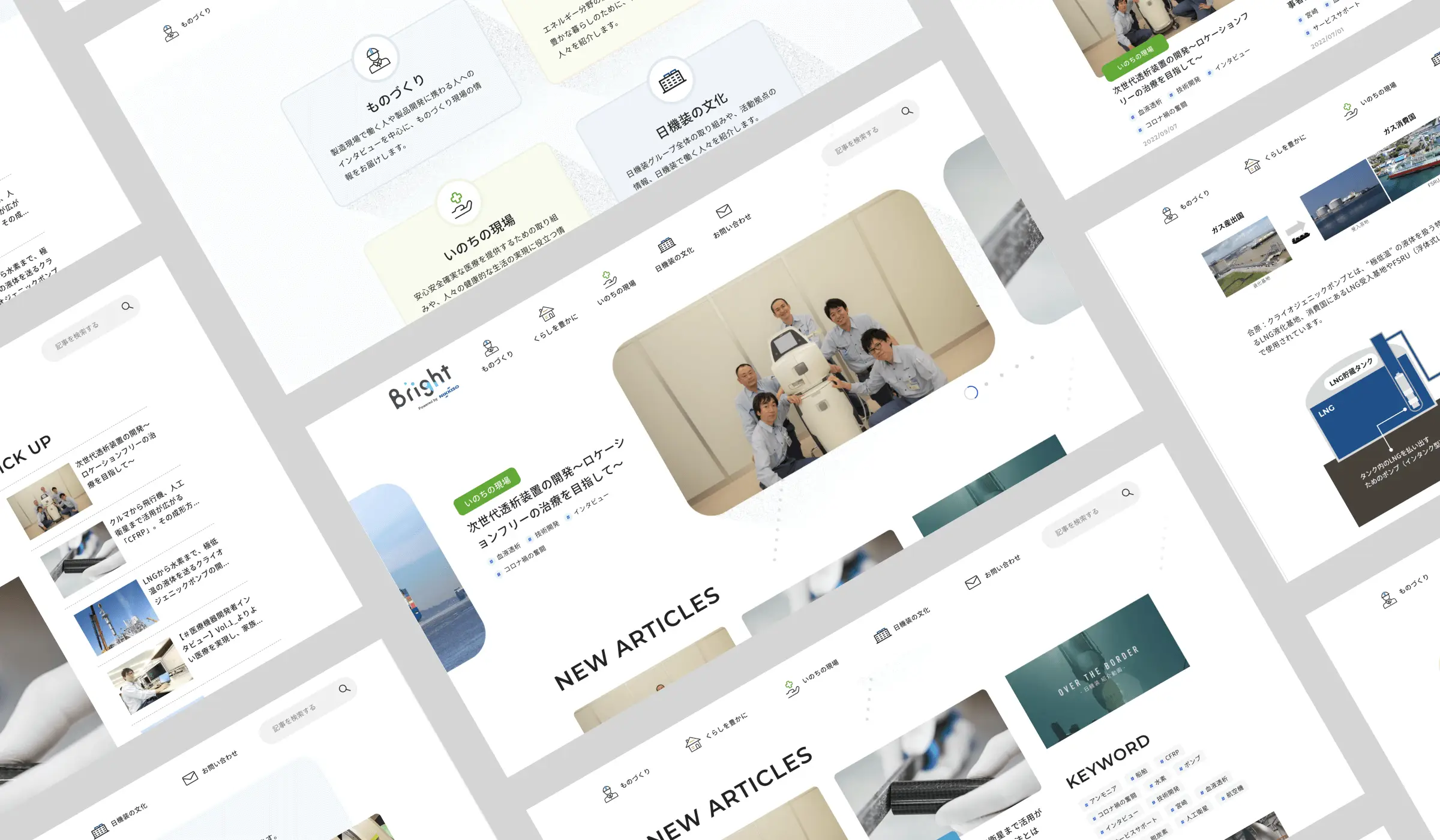近年SNSとホームページの連携をマーケティングに活かす運用方法が一般的になっています。SNSでの情報発信は手軽な反面、リソースばかりかかってしまい集客や成約にあまり結びつかないといったケースも少なくありません。
本記事では、SNSとホームページを連携させることで得られるメリットやデメリット、方法について詳しく解説します。効果を出すために注意するポイントについても紹介するので、ぜひ参考にしましょう。
ホームページとSNSを連携させる6つのメリット・目的
SNSとホームページを連携させるメリットは主に次の6つで、これらのメリットを目的にホームページとSNSの連携は行われます。
- ユーザーとのコミュニケーションを増やす
- ブランドや商品の認知度を向上させる
- ユーザーのホームページ訪問を促進させる
- Webサイトの滞在時間を伸ばせる
- ターゲットのリアルな声を聞ける
- カスタマーサポートの役割も果たせる
1. ユーザーとのコミュニケーションを増やす
SNSの強みは双方向のコミュニケーションが取れる点です。ホームページだけでは企業からの一方的な発信となってしまい、ユーザーとのコミュニケーションを十分に取ることができません。
SNS上での質問やクレームに対応する、ユーザーの日々の投稿にアクションを起こすなどすることで、ユーザーとの信頼関係を築くことができます。
さらにまたSNSで継続的に発信し、他のユーザーとのコミュニケーションをとることにより、ユーザーをファンにしやすくファンの獲得がしやすくなります。担当者や会社の価値観や世界観をSNSを通じて発信することで、自社へのロイヤリティ構築長期的なファンづくりにも繋がるでしょうが可能となることも。
2. ブランドや商品の認知度を向上させる
SNSでの情報発信は、ブランドやブランドの認知度を高めるために非常に有効です。SNS上で継続的に情報を発信することによってユーザーがブランドやブランドを認知する、または思い出す機会が増え、結果として成約やリピートの獲得につながります。
またSNSで継続的に発信し、他のユーザーとのコミュニケーションをとることにより、ファンの獲得がしやすくなります。担当者や会社の価値観や世界観をSNSを通じて発信することで、長期的なファンづくりが可能となることも。
何よりSNSの発信は費用がかかりません。気軽に宣伝活動が出来るツールとして非常に便利です。
3. ユーザーのホームページ訪問を促進させる
商品やサービスについて知りたいユーザーは
- パソコンで詳細な情報をじっくり確認・比較したい層
- スマホで手軽に最新情報を手に入れいたい層
の2つに分けられます。そこでSNSとホームページを連携させればることでSNSからホームページへ、もしくはSNSからホームページへのアクセスを促すことが可能です。これによりユーザーは詳細な情報も最新情報もスムーズに得ることができます。
また、SNS上でブログ記事やサービスの紹介を行うことでホームページへの訪問を促進することができ、ホームページ内でSNSを紹介することでSNSへのアクセスを促すことができます。
4. Webサイトの滞在時間を伸ばせる
SNSとWebサイトを連携させることで、サイト滞在時間を伸ばすことも可能です。例えば、アパレル企業がInstagramの公式プロフィールでWebサイトのURLを載せておけば、Instagramの投稿写真が気に入ったユーザーはWebサイトを訪れるでしょう。Webサイト内は他の商品情報も充実しているので、気に入った商品以外の商品も巡回して閲覧します。こうして、サイト滞在時間を伸ばせるだけでなく、気になった商品以外の商品購買に至る可能性が高まるでしょう。
WEB接客ツールFanplayr社とイタリアのボッコーニ大学の調査※では、Webサイトに「長く滞在するユーザーほど、購入する可能性が高い」と報告しています。このことからSNS連携でサイト滞在時間を増やすことは、商品売り上げに貢献する可能性も高いと言えるでしょう。(参照:ECの味方ミカタ「心地よい購入体験がリピートを呼ぶ、行動分析で見えたCVRアップ法」)
また、サイト滞在時間の副次的な効果として、直帰率の減少があります。SEOのトレーニングおよびエキスパート情報サイトBACLINCO※は、Googleの検索表示の順位と直帰率には関係があると発表しています(参照:BACLINCO「What Is Bounce Rate?」)。言い換えれば、直帰率を減少させることは、SEO効果があるということです。
5. ターゲットのリアルな声を聞ける
SNSを活用することでターゲットのリアルな声を聞くことができ、自社商品やサービスの改善案へとつなげることができます。例えば、気になる発言をしているユーザーに対して、SNSなら気軽にDMやリプライを送ることでコミュニケーションを図れるのも魅力の一つです。さらにターゲットのリアルな声を利用して、UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)として宣伝材料にもなるでしょう。
6. カスタマーサポートの役割も果たせる
SNSを利用していると、ターゲットの率直な「ここがわかりづらい」などの意見を見ることがあります。この時自社で改善すると同時に、ターゲット層に対して投稿という形で「〜の基本的な使い方」「〜な時はこうするのがおすすめ」といった内容を発信することで、同じように悩んでいるユーザーに対し解決を促すことが可能です。
実際にSHARP株式会社は、毎年夏前になると「エアコンの試運転をするように」といった内容の投稿を行い、毎年多くのエンゲージメントを獲得しています。
このように、 SNSの利用はカスタマーサポートの役割も果たすのです。
ホームページとSNSを連携させる3つのデメリット
SNSとホームページを連携させることには、以下のようなデメリットもあります。
SNSの投稿が手軽な反面、情報の質が落ちる可能性がある
過去のSNS投稿からの流入は期待できない
SNSとホームページでの情報の整合性に注意が必要
これらデメリットと対策方法を知った上で、ホームページとSNSの連携について考えていきましょう。
SNSへの投稿が手軽な反面、情報の質が落ちる可能性がある
SNS上での投稿は手軽ですが、情報の質が落ちる可能性があります。
情報の質が落ちてしまう理由は次の二つです。
ホームページと異なり、SNS上の投稿は文字数制限があり投稿者の意図した通りに伝わらない可能性があるため
ホームページの担当者が一人でSNS運用を兼ねる場合、リソースが足りない中で一定数の投稿を行わなければならないため
これらの問題を解決せずにターゲットとなるユーザーに誤解を与えてしまう投稿を続けていくと、最悪の場合炎上の可能性も。
担当者はホームページとの性質の違いを理解し、情報を簡潔に伝える意識に加え、情報の出し方を変更するなどの工夫を行う必要があります。またリソース不足で投稿内容を熟考できない可能性がある際には投稿前の社内チェックを行う、可能であればSNS運用担当者をホームページの運営担当者と分けて工数を分散させる、などの体制構築が必要です。
過去のSNS投稿からの流入は期待できない
ホームページには「なんらかの検索キーワードで検索結果上位に表示されれば継続的な流入がある」特徴に対し、 SNSは過去の投稿からの流入はあまり期待できません。SNSとホームページで二重に工数がかかることにもかかわらず資産性がないため、デメリットに感じやすい部分かもしれません。
一方でSNSにはホームページにはあまりない拡散性や、プラットフォーム内での大量のユーザーによる閲覧の可能性があり、一長一短です。だからこそ、SNSとホームページを連携して短期的な流入を提供するSNSと、長期的な流入を確保しやすいホームページの両輪で進めていくのが確実といえます。
SNSとホームページでの情報の整合性に注意が必要
SNSとホームページでの情報に相違がある場合、ユーザーからの信頼を失うことがあります。このケースはSNSの投稿やホームページの記事作成を外注している場合に起こりやすく、レギュレーションを作成し発信する数字を揃えておく、投稿のチェックをする人は記事のチェックにも関わるなど、SNSとホームページでの情報の整合性を担保するための運用が必要となります。
特にSNSでは文字制限があるので、自動投稿機能を使うと内容が途中で表示されなくなってしまう可能性もあります。そこで、SNSに投稿した際の文字制限を把握しておきましょう。
- X(旧Twitter)の文字数制限:140文字
- X(旧Twitter)有料会員の文字数:12,500文字
- Instagramの文字数制限:2,200文字
ホームページとSNSを連携させる方法
ホームページとSNSを連携させるには次の5つの方法が一般的です。
SNSシェアボタン
ホームページの記事公開時の自動投稿機能
SNSでのホームページリンクの登録
SNS埋め込みコードを利用した記事内での紹介
SNS投稿へのホームページリンクの設置
1. SNSシェアボタン
SNSシェアボタンとは記事の上下や左右にある、SNSのアイコンです。 SNSシェアボタンを押すと、SNSアプリの投稿画面が立ち上がり記事を簡単にSNSにシェアできるようになっています。
魅力的な記事の制作と合わせてSNSシェアボタンを設定することで、自社ホームページの拡散とサイテーション(SNSでのホームページへのリンクを伴わない言及)さらに被リンクを獲得できるチャンスとなります。これによりSEO効果も期待できるのでホームページ制作の際はぜひSNSシェアボタンを設置しましょう。
SNSシェアボタンが押されやすい配置場所は以下の3カ所です。
- 記事タイトルの真下
- ページの最下部
- 1スクロールごとに追加
2. ホームページでの記事公開時の自動投稿機能
ホームページでの記事公開時のSNSへの自動投稿機能についても、ホームページ作成の際にはぜひ実装をしておきましょう。
この機能があると、記事公開の際に定型文とともに新規投稿記事をSNSに自動で宣伝してくれます。しかし定型文と比べ、きちんと投稿内で記事の内容をまとめて訴求を行う方がホームページへの誘導率は上がる傾向があるので、この機能を利用するかどうかは運用体制次第ともいえます。
3. SNSでのホームページリンクの登録
SNSのプロフィールページにてホームページへのリンクを登録しておくことも、重要な連携の一つといえます。
ユーザーの動線としては、どのSNSであっても「興味のある投稿をしているアカウントを見つけた」→「このアカウントの他の投稿を見てみよう」という流れで主にプロフィールページに訪れます。この時にプロフィールページからホームページに飛べるようにしておくことで、SNSに興味を持ってくれたターゲットに属性が近いユーザーがホームページに訪問してくれるのです。
4. SNS埋め込みコードを利用した記事内での紹介
SNS埋め込みコードを利用して、SNS投稿をホームページの記事内で紹介することもSNS連携の一つです。ホームページに表示されるSNS投稿の見た目がSNS上での投稿画面そのままなので、ホームページを閲覧しているユーザー側としても、ホームページの内容とSNS投稿内容の違いがはっきりとわかります。
埋め込みコードの利用メリットとしては次の通りです。
自社のSNSでの発信内容を二次利用できる
ホームページでの滞在時間を伸ばすことができる
UGC(ユーザーの情報発信のコンテンツ)として利用可能
「自社のSNSでの発信内容を二次利用できる」については、ホームページとSNSの連携でのデメリットの部分で紹介した「SNSについては流入獲得に寄与しづらい」部分へのカウンターとなるのではないでしょうか。また最後のUGCについては、ターゲットとなるユーザーのコメントや質問に答える形での記事とすることで、ブログ記事テーマの幅を広げることに利用可能です。
5. SNS投稿へのホームページリンクの設置
ほとんどのSNSにおいてプロフィールページだけでなく、SNSの投稿にもホームページリンクの設置が可能です。ホームページ内のブログ記事や自社商品・サービスページ、ホームページリニューアルの際にはサイトのデザインがわかるスクリーンレコードとトップページへのリンクなど、投稿にリンクを貼るシチュエーションは多数あります。
積極的にSNS投稿からホームページへの流入を狙っていきましょう。
効果を出すためのホームページ×SNSで気をつけること
成果を出すためのホームページとSNSの連携した運用方法で気をつけることは次の3つです。
ターゲットの設定
運用体制を構築する
効果測定を行う
ターゲットの設定
ホームページとSNSを連携する前に会社として、もしくはサービスとして狙っていくターゲットの設定を行いましょう。なぜならSNSによってユーザーの属性、好みのコンテンツ、情報発信の方法が異なるからです。まずはターゲットを明確にして、どのSNSを使用するかをしっかり検討しましょう。
またターゲット像をペルソナとして運営チームで共有することで、狙うべきコミュニティが絞れるなどのメリットがあります。
無料配布資料「ペルソナ設計入門ガイド」では、ペルソナを設計するためのワークショップ手法を詳細に解説しています。どのユーザーに向けて発信するか明確に決まっていない場合はぜひ下記より無料でダウンロードして参考にしましょう。
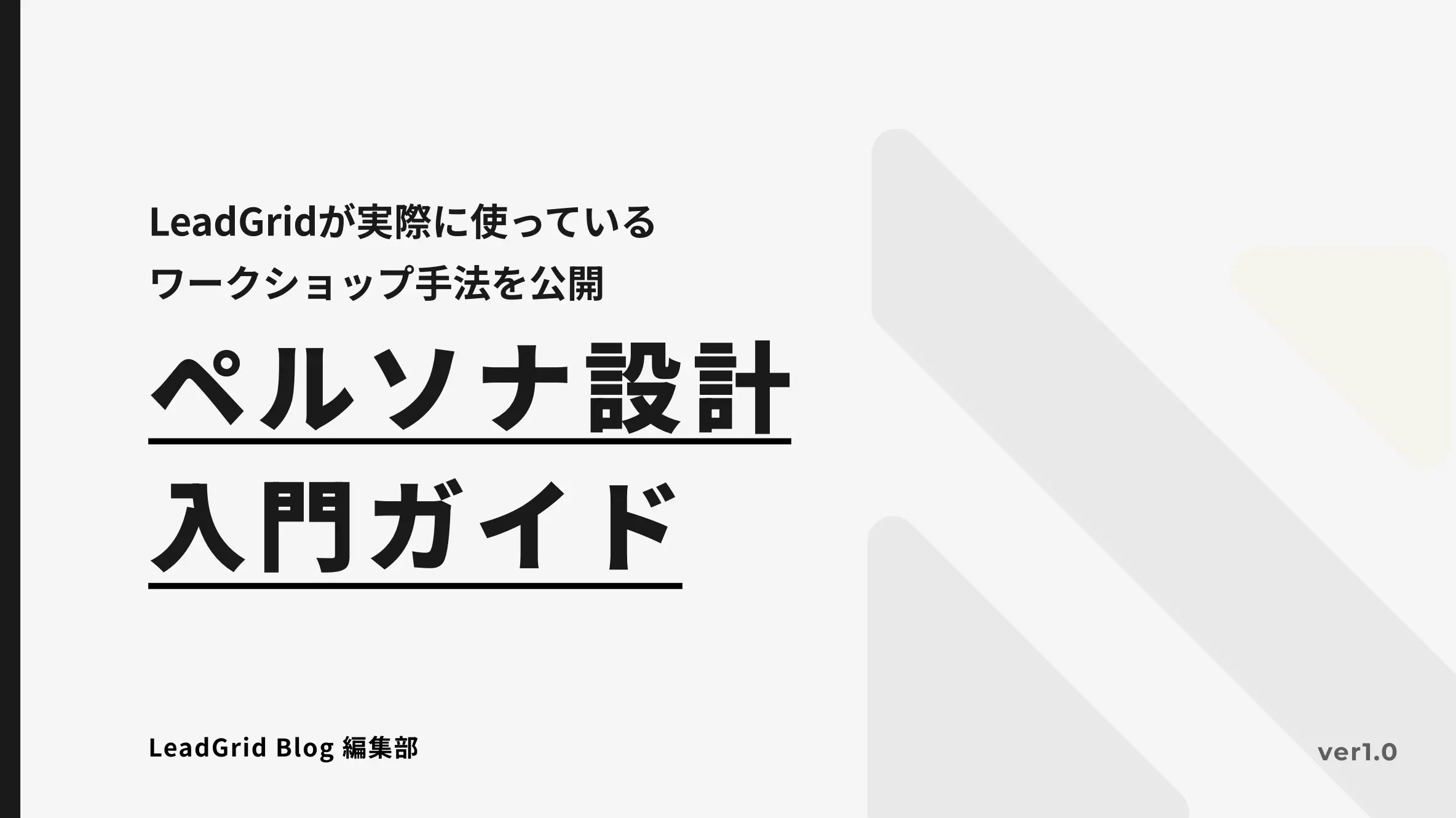
運用体制を構築する
とくにSNSに関しては、運用が属人化しがちです。SNSアカウントはあくまで会社のアカウントであり、担当者はいつまでもSNSの担当ができるとは限りません。 担当が変わってパフォーマンスが落ちる前に運用体制を構築し、特定の人物に頼らなくても継続的に情報発信が続けられるようにしましょう。
またホームページ運営についても同じことがいえます。こちらの資料ではオウンドメディアにはなりますが、運用体制構築についてのマニュアルを無料公開しているので、必要に応じてぜひダウンロードしましょう。
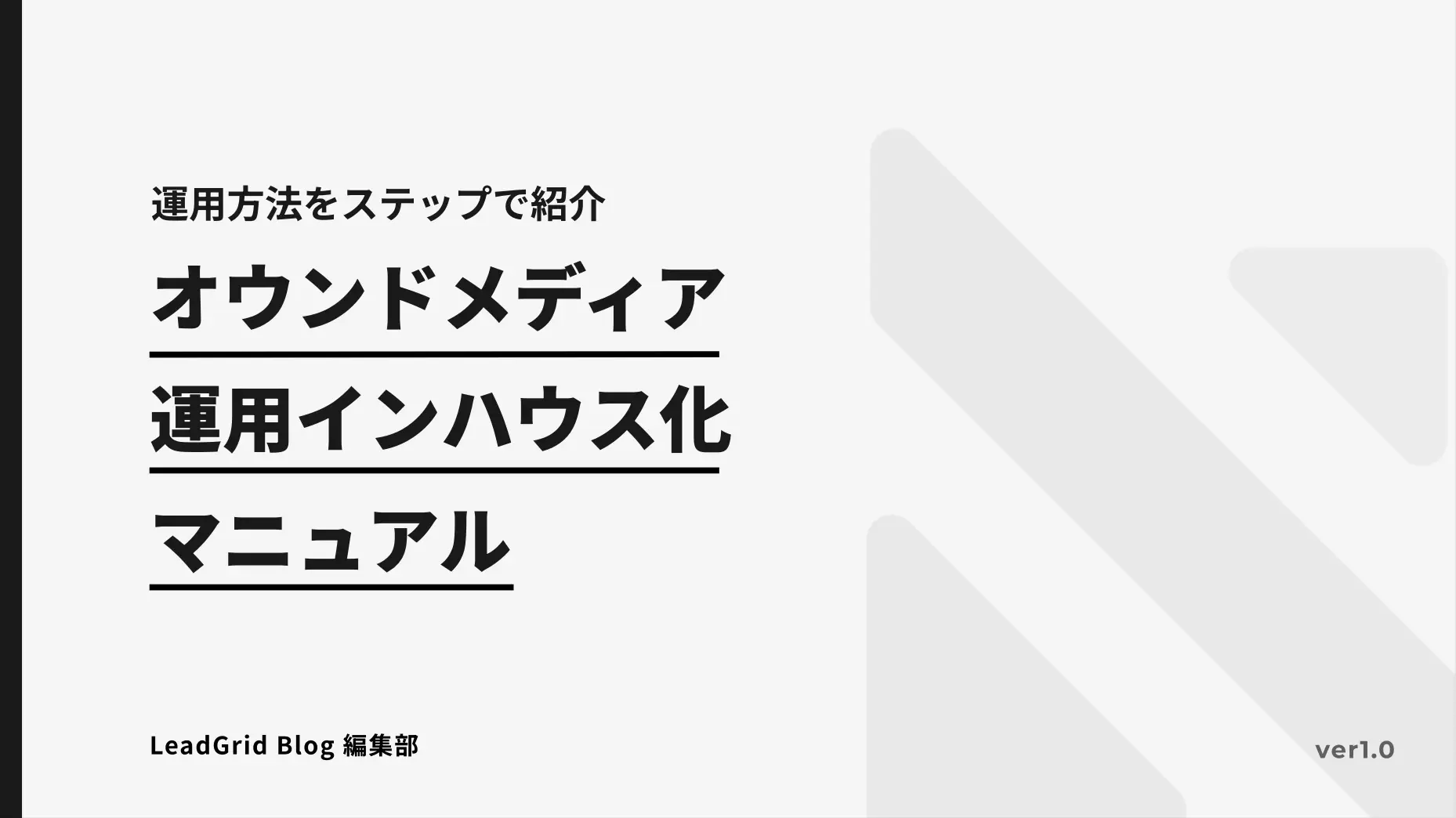
効果測定を行う
定期的な効果測定もホームページとSNSの連携を進める上では重要です。
SNSの場合は媒体にもよりますが、投稿ごとのエンゲージメントやフォロワー数の推移、ホームページへの遷移数が主な指標になります。SNS内で確認できるアナリティクスページや、サードパーティの分析ツールで効果を測定しましょう。
ホームページに関してはアクセス解析や流入元分析によりどこからユーザーが来ているのか、ヒートマップでどの部分が読まれているのか、コンバージョン分析によりパフォーマンスの高いページはどこなのか、などについて測定する必要があります。
ホームページの分析に関する詳細は下記の記事で紹介しているので、分析について落とし込めていない方はぜひご覧ください。
関連記事:Webサイトの分析方法|分析の種類やツール、ポイントについても
はじめからSNS連携機能が実装されているCMSを選ぼう
この記事ではホームページとSNSを連携させる目的やメリットやデメリット、連携させる方法について解説しました。ホームページとSNSを連携し、ホームページへの流入動線を確保しつつターゲットリサーチの参考にしましょう。
ただSNSシェアボタンや新規記事公開時の自動SNS投稿機能については、ホームページ制作段階で実装してしまうのがおすすめです。後付けでプラグインなどで実装すると既存のプラグイン同士が干渉を起こす、アップデートの際に不具合を起こすなどの可能性があります。
そこで はじめからSNS連携が機能として実装されているCMSでホームページ制作をするのがおすすめです。はじめから機能として盛り込まれているので実装も簡単、機能同士が不具合を起こす可能性も低くなります。

株式会社GIGがホームページ制作の際に使用するCMSであるLeadGridも、SNS連携が標準機能として実装されています。スムーズなホームページとSNSの連携が可能です。
またLeadGridは「ブログ機能が一般向けのブログサービスのようで使い勝手のいい」と定評があります。ホームページの安定した更新には、ブログ機能が使いやすいことは重要なポイントです。
継続的な情報発信をホームページとSNSの両方でサポートするLeadGridの詳細はこちらからどうぞ。
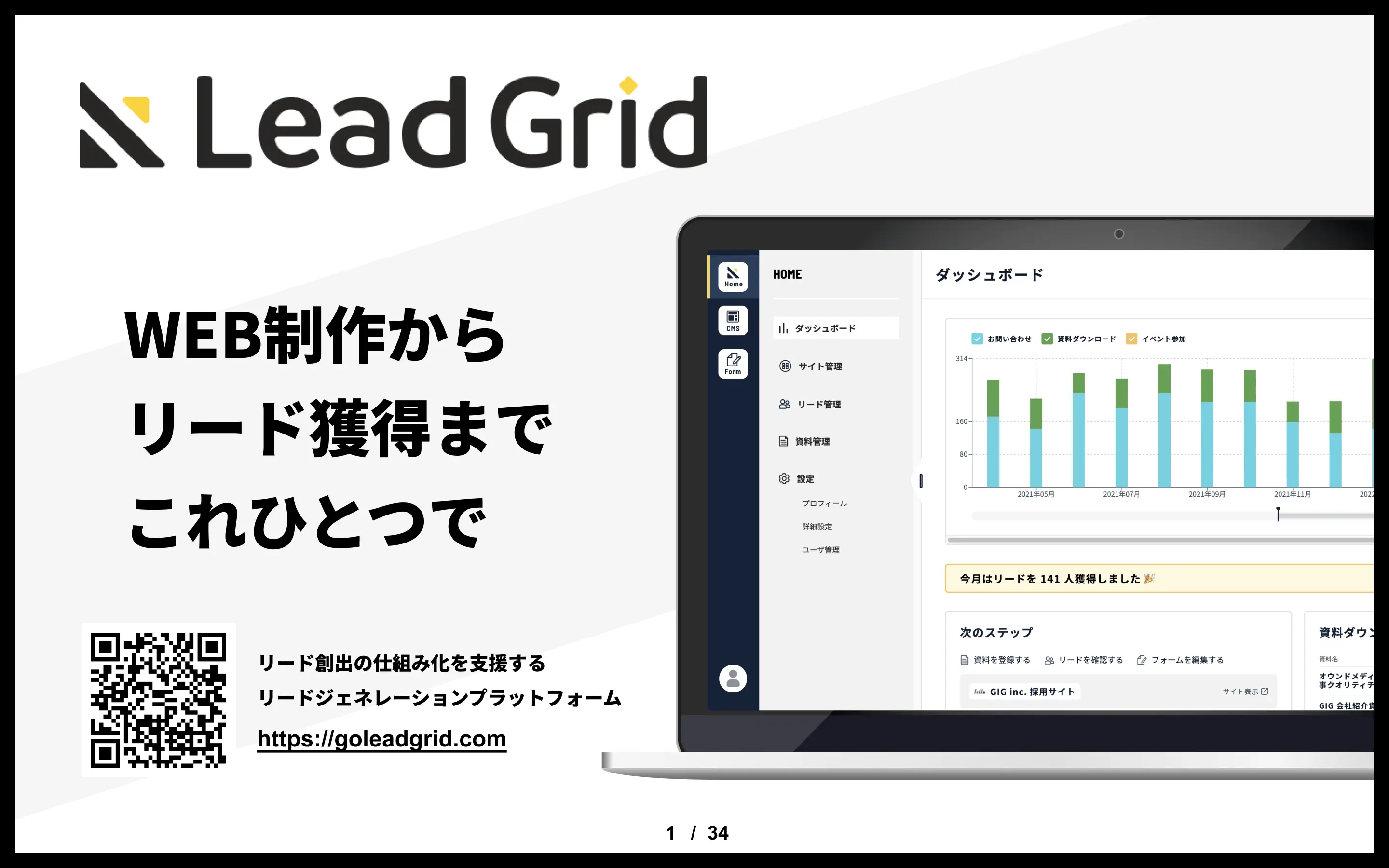
LeadGrid BLOG編集部は、Web制作とデジタルマーケティングの最前線で活躍するプロフェッショナル集団です。Webの専門知識がない企業の担当者にも分かりやすく、実践的な情報を発信いたします。
関連記事
Interview
お客様の声
-
SEO・更新性・訴求力の課題を同時に解決するため、リブランディングとCMS導入でサービスサイトを刷新した事例
ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社 様
- # サービスサイト
- # 問い合わせ増加
- # 更新性向上
 Check
Check -
「SEOに閉じないグロースパートナー」へ想起転換したコーポレートサイト刷新の事例
株式会社LANY 様
- # コーポレートサイト
- # リブランディング
- # 採用強化
 Check
Check -
企業のバリューを体現するデザインとCMS刷新で情報発信基盤を強化。期待を超えるサイト構築を実現した事例
株式会社エスネットワークス 様
- # コーポレートサイト
- # 更新性向上
 Check
Check -
採用力強化を目的に更新性の高いCMSを導入し、自社で自由に情報発信できる体制を実現した事例
株式会社ボルテックス 様
- # 採用サイト
- # 採用強化
- # 更新性向上
 Check
Check
Works