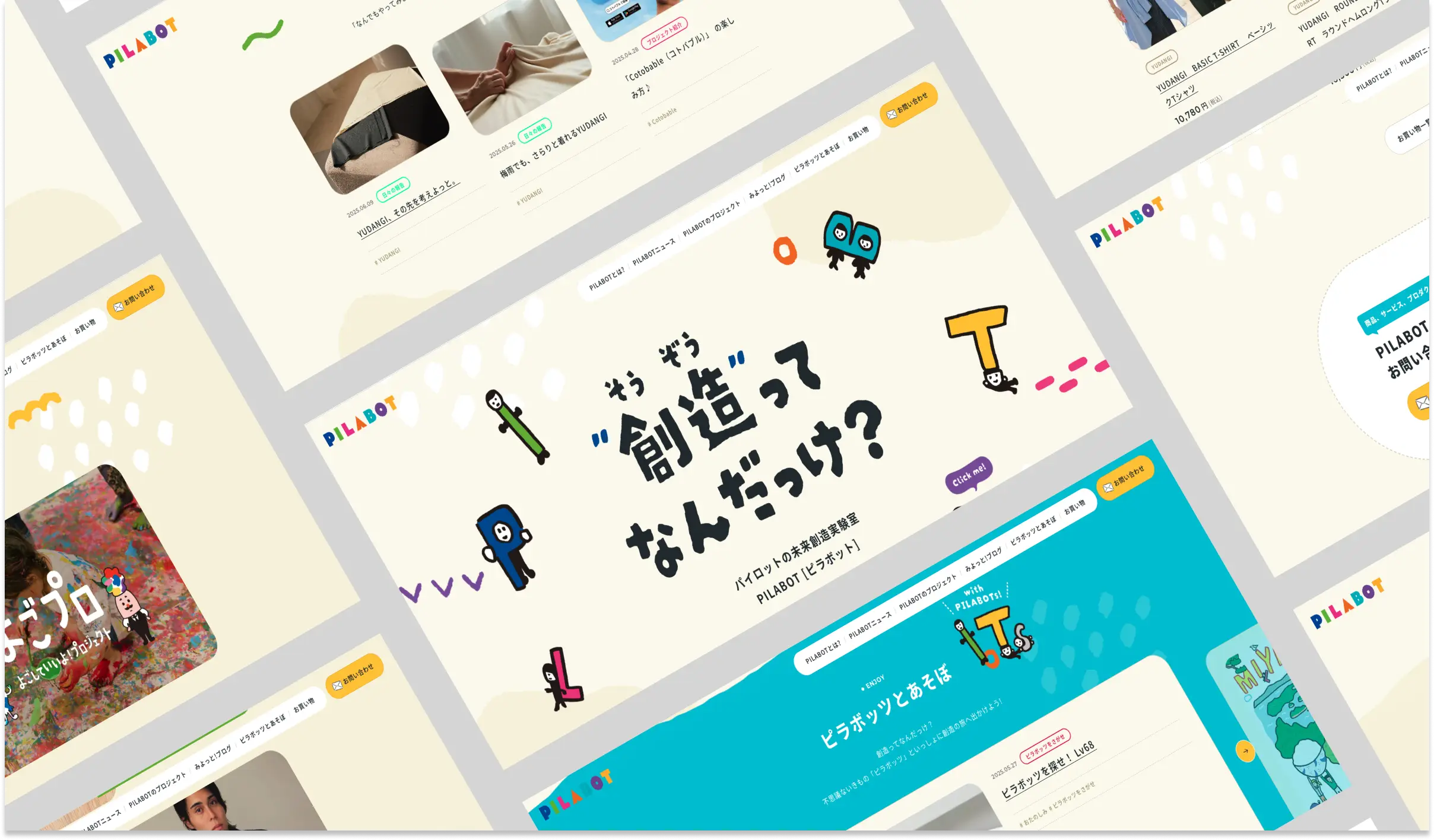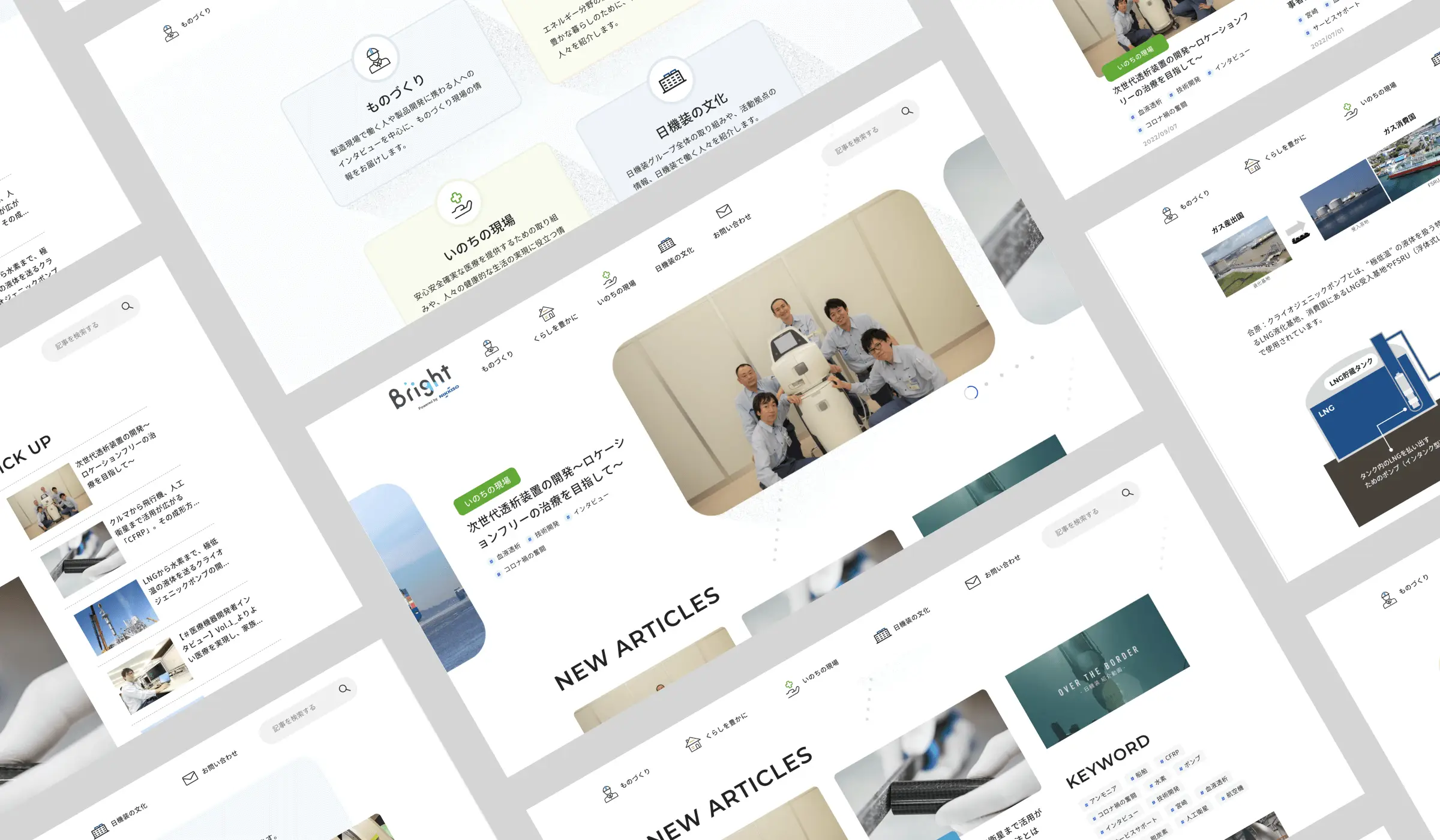ブログのカテゴリ分けの方法とは?SEOに重要な理由とコツについても
ブログのカテゴリ分けの方法とは?SEOに重要な理由とコツについても
今すぐ試せる、CVR改善リストを無料配布中!
CVRを今すぐ改善したい担当者様へ。業界別のCVR平均値をもとに、CVR改善ポイントを15個リストアップした資料をご用意しました。この後の業務からぜひご活用ください。
ブログ運営において、カテゴリー分けは重要な要素です。しかしその方法やSEOに及ぼす影響については十分に理解しないままに「なんとなく」で分けてしまっていないでしょうか。
この記事ではカテゴリー分けの基本的な考え方やSEOへの効果、さらに効果的なカテゴリー分けのポイントについて詳しく解説していきます。
記事を読み進めることで、ブログのカテゴリー分けに対する理解が深まり、自社サイトのブログに適したカテゴリー分けの方法を見つけることができるでしょう。
なお、カテゴリー分けを含むSEOに取り組みたい方は無料配布資料「SEOに強いサイトにするための制作・運用チェックシート36項目」もあわせてご活用ください。サイトの制作〜運用までの各フローにおいて必要なSEO施策を、漏れなく実行できているか確認できるチェックシートになります。下記より無料でダウンロードできます。
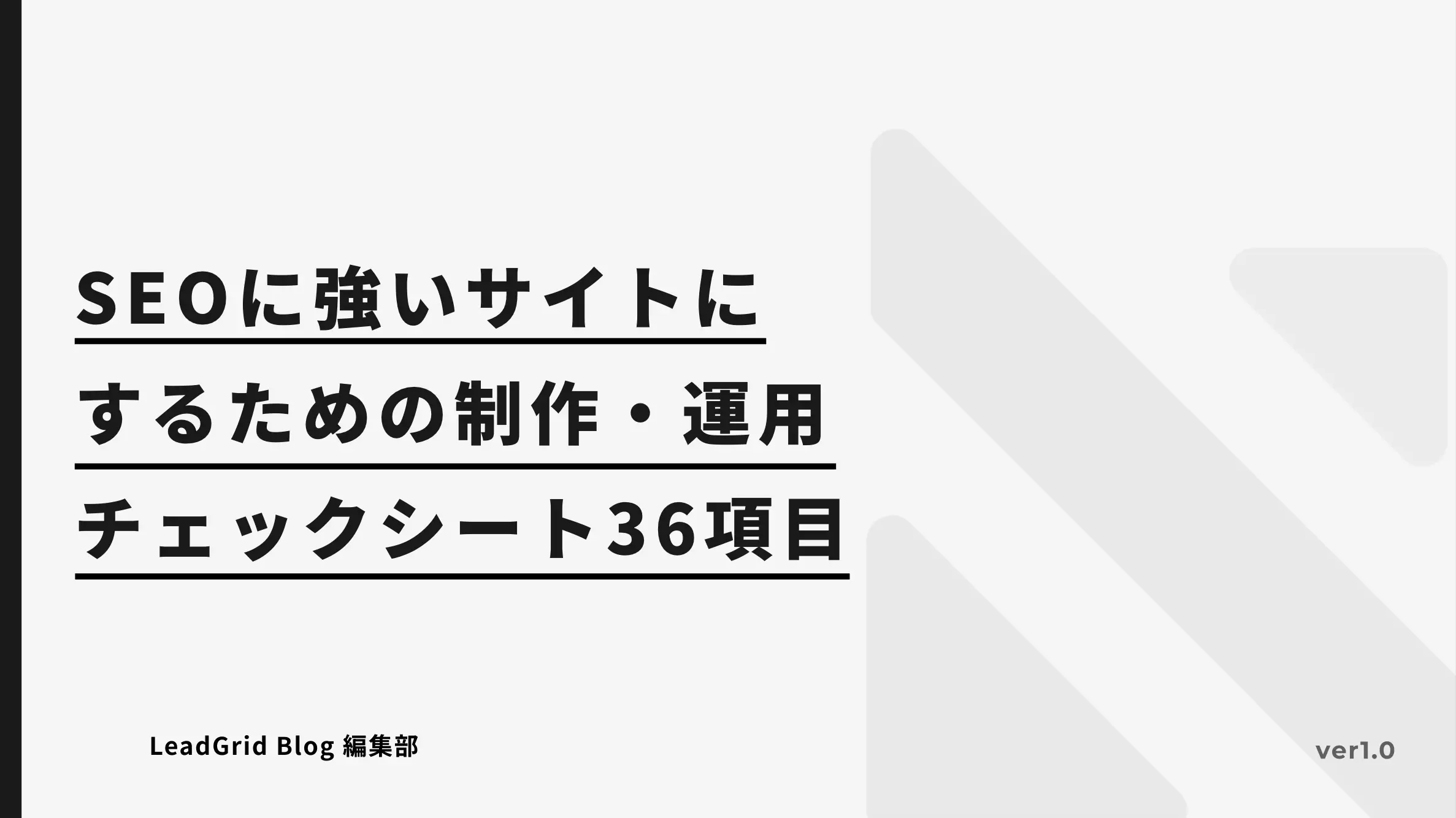
そもそもカテゴリー分けとは
カテゴリー分けとは、Webサイトやブログなどのコンテンツをテーマごとに分類し、ユーザーがサイト内の構造を把握できるようにするものです。
ユーザビリティや検索エンジンの最適化において、カテゴリー分けは重要な役割を担います。
たとえば、長期間にわたってブログを運営すると、さまざまなテーマのコンテンツが増えるため、サイトを訪れたユーザーが情報を探すのが困難になります。
カテゴリー分けされていないと適切な記事を探しづらく、読者の離脱率が高まる原因となってしまうのです。
そこで有効なのがカテゴリー分けの手法です。適切にカテゴリー分けすることで、ユーザビリティが向上し、SEOに好影響をもたらすことが大きなメリットです。
また、ユーザーの離脱率低下などにもつながるため、サイト運営においてカテゴリー分けは欠かせない施策と言えるでしょう。
単にカテゴリー分けをすればよいわけではなく、カテゴリー名や数、記事数などを考慮することが大切です。
ブログのカテゴリー分けがSEOにおいて重要な理由
カテゴリー分けはWebサイトの情報をブログ記事ごとに整理し、ユーザーが求める情報に素早くアクセスできるようにするための手法です。主にキーワード選定時に行います。
関連記事:SEOキーワード選定の方法6ステップ|おすすめツールや注意点も
ここではカテゴリ分けがSEOやサイトの運営にどのように影響するのかについて、解説します。
クローラビリティの向上
クローラーとはGoogleなどの検索エンジンがWebサイトの情報を収集するために使われるプログラムのことです。クローラーがサイトを効率的に巡回し、情報を収集できるようにすることで、検索結果に表示される可能性が高まります。
関連記事:クローラーとは?仕組みやSEOにおけるインデックス対策について
適切なカテゴリー分けを行うことで、クローラーがサイト内の情報を効率的に巡回できるようになり(クローラビリティの向上)、SEOへの好影響が期待できます。
ユーザビリティの向上
ユーザー目線に立った適切なカテゴリー分けにより、カテゴリによる記事の絞り込みが可能となります。それにより、ユーザーが目的の情報を簡単に見つけ出すことができるため、ユーザビリティが向上します。
ユーザビリティ向上により、ユーザーがサイトに滞在する時間が長くなる、サイト全体を通して検索ニーズ(ブラウザを開いた理由)が解決されるユーザー行動履歴を検索エンジンに送れるなどの理由から、検索エンジンがWebサイトの価値を高く評価することにつながります。
カテゴリの分類が適切ではない場合の問題点
適切でないカテゴリー分けがもたらす問題としては、主に以下が挙げられます。
ユーザーが目的の情報にたどり着きにくくなる
サイトのユーザビリティが低下する
検索エンジンがサイトの情報を正確に評価できなくなる
上記問題からSEOに悪影響が出ることに加え、Webサイトの使い勝手が悪いこと自体がユーザーのWebサイト、ひいてはWebサイトで取り扱っているサービスへの不信感につながりやすくなります。「個別の記事は悪くないのに、思ったような成果が出ない」という場合はカテゴリ分けを含む、ユーザビリティの改善を検討してみましょう。
なお、サイトのユーザビリティを見直すときは無料配布資料「CVR改善チェックリスト」が役に立ちます。ユーザビリティの低下はSEOだけでなく、お問い合わせや購入といったコンバージョンの減少にも密接に関わるため、課題点を洗い出して適切な改善施策を実行する必要があります。この資料では改善点を見つける時に注目してほしい箇所と改善アドバイスをチェックリスト形式でまとめております。下記より無料でダウンロードできるため施策の指針を決める際に参考にしてください。
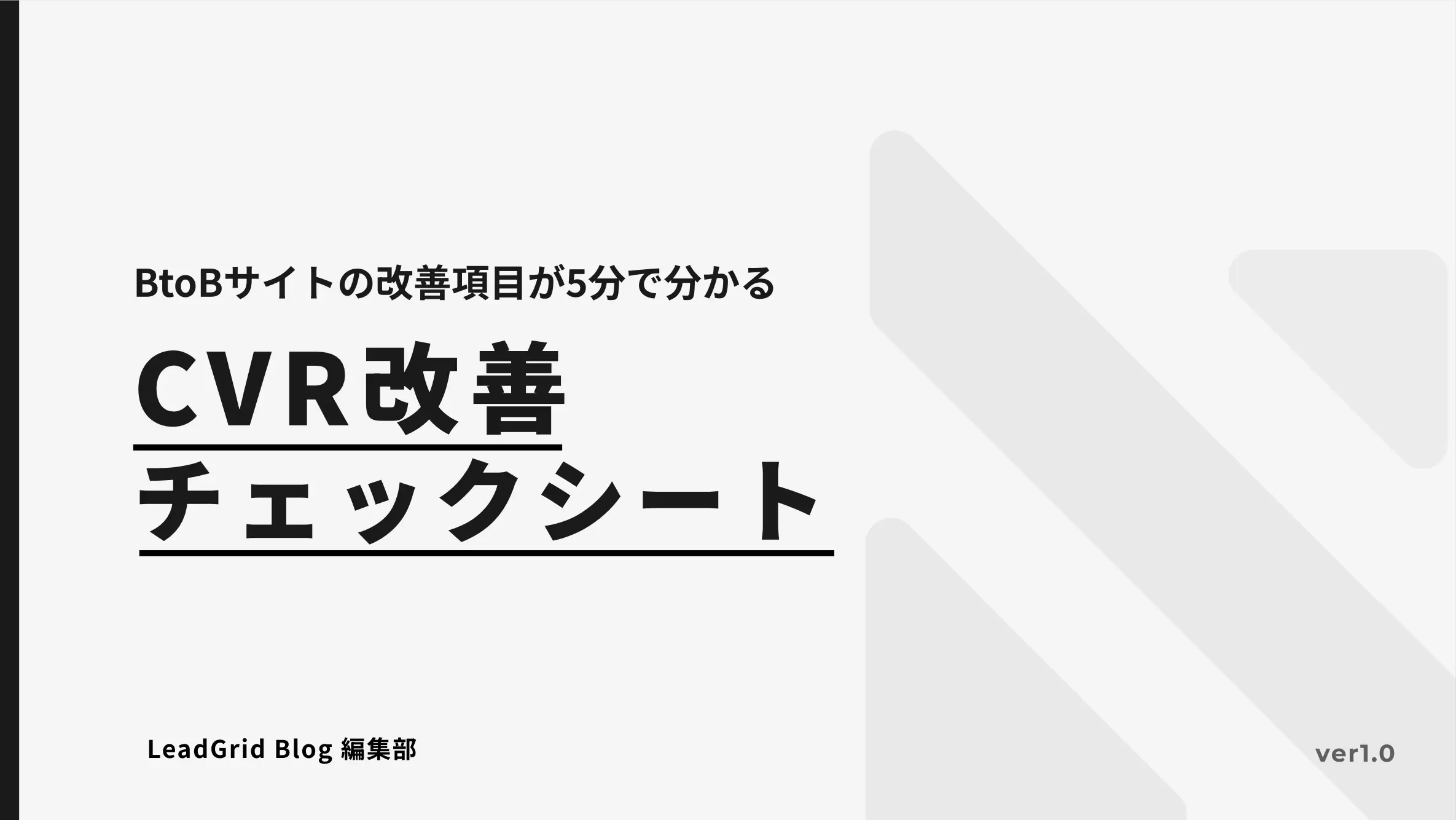
カテゴリー分けの手法
カテゴリ分けは主に、グルーピングとカテゴリページの設置が主な施策となります。
グルーピングによる階層構造の作成
コンテンツを関連性の高いグループにまとめて、階層構造を作成しましょう。「Webマーケティング→SEO」「Web広告→リスティング広告」といった具合です。階層構造のグルーピングにより、ユーザーが効率的に記事を絞り込むことができ目的の情報にたどり着きやすくなり、サイトのユーザビリティが向上します。また検索エンジンとしてもサイト内の情報の関連性がよりわかりやすくなり、SEO効果も期待できます。
カテゴリページの設置
階層構造に分けた各カテゴリーに対して、カテゴリページを設置しましょう。カテゴリページとは、そのカテゴリーに属する記事コンテンツへのリンク一覧を新着順で表示するページです。カテゴリページによりユーザービリティ向上が見込めるほか、カテゴリページに情報が網羅されていると検索エンジンに認識されることで、カテゴリページ自体が検索上位に掲載されることも。
カテゴリページには、そのカテゴリーに関する説明文やキーワードを含めて検索エンジンに内容をアピールしましょう。
カテゴリー数の適切なバランス
カテゴリー数が多すぎると、ユーザーが迷ってしまうことがあります。初期段階でカテゴリ数を増やしすぎると、それぞれのページに1、2記事しかなく「むしろ探しづらい」状況にも。
逆に、記事数に対してカテゴリー数が少なすぎると、情報が整理されず、ユーザーが目的のコンテンツを見つけにくくなります。カテゴリー数はサイトの規模や内容に応じて適切なバランスを見つけましょう。
カテゴリ分けの3つのコツ
ここからは、カテゴリ分けを行うにあたり3つのコツを紹介します。
カテゴリの階層は第二階層までにする
タグも利用する
パンくずリストかURLでサイトの構造がわかるようにする
1. カテゴリの階層は第二階層までにする
カテゴリの階層は第二階層まで、多くても第三階層までにしましょう。例えば以下の通りです。
第一階層:Web集客
第二階層:SEO
第三階層:記事制作
第四階層以上にすると、四階層目のWebサイト上での表現が難しくなり、かえってユーザービリティを損ねてしまいます。
2. タグも利用する
カテゴリだけでは分類の数が多くなりそうな時は、タグも利用しましょう。タグとはカテゴリとは別に記事ごとに設定できる、記事の特性を示すものです。カテゴリの数は大枠だけにしておいて、カテゴリで分けきれない小さな分類については、タグを使用するようにしましょう。
例えばLeadGridBlogでは執筆現在、カテゴリは「Webサイト制作」「リード獲得」「Webマーケティング」「CMS」の4つにしており、タグで「サービスサイト」「コーポレートサイト」など小さな分類をおいています。こうすることで「サービスサイトの制作費用」がテーマの記事であればタグを「サービスサイト」にした上で、カテゴリを「Webサイト制作」にし、「サービスサイトの集客方法」がテーマの記事であればタグは同じく「サービスサイト」でありながらカテゴリを「Webマーケティング」にできるなど、柔軟な設定が可能です。
3. パンくずリストかURLでサイトの構造がわかるようにする
パンくずリストかURLを用いて、ユーザーが今いるページのWebサイト内での立ち位置がわかるようにしましょう。
パンくずリストとは、現在表示されているページのWebサイト内での位置を示すナビゲーションです。「home>カテゴリ>タイトル」といった順番で表されることが多く、例で言う「home」や「カテゴリ」部分にはテキストリンクが設定されており、リンクを伝ってカテゴリページにアクセスできるようになります。
またURLを用いるとは、ディレクトリの構造を用いてURLを「https://xxx.com/blog/category/contents」とすることで、URLを見ればどのカテゴリかわかり、URLの個別記事部分を消せば(「https://xxx.com/blog/category/」にすれば)カテゴリページにアクセスできる、という状態にすることです。
■関連記事
URLをカテゴリと紐付けてしまうやり方は、後々の運用上の都合でカテゴリ変更があった際にURLが変更されてしまい検索エンジンからの評価がリセットされてしまう恐れがあるため、おすすめはパンくずリストです。
4. テーマにマッチしたカテゴリに配置する
サイトで扱う主要なテーマや、ページのトピックに合わせてカテゴリー分けすることで、Webサイトの専門性を高めることができます。また、特定のテーマに興味のあるユーザーを効率良く集められることもメリットです。
たとえば、Webマーケティングに関するサイトを運営している場合に、「SEO」「SNS」などのカテゴリーを作るのは問題ないでしょう。
しかし、自社のWebサイトとの関連性が低いカテゴリーを作成することは、サイトの専門性を下げてしまう要因になりかねないのでおすすめできません。
5. ユーザー視点を意識する
カテゴリー分けを行う際は、常にユーザー視点であることを意識しましょう。
たとえば、ECサイトの場合、ユーザーは以下のような思考で商品を探します。
レディースの服が欲しい:性別の選択
ドレスが欲しい:種類の選択
ミニ丈が欲しい:細かいデザインの選択
このように、大きなカテゴリーから細分化していくことで、ユーザーの目的に合ったページへとスムーズに誘導することができます。
ユーザー視点でカテゴリー分けを行うことで、ユーザビリティを高められるでしょう。
6. ページ数を考慮する
カテゴリー傘下に含まれるページが少ない場合は、検索エンジンに「専門性が低い」と判断される場合があります。また、Webサイトを訪れてカテゴリー検索したユーザーからも期待外れだと感じさせてしまうかもしれません。
まずは、一定数のページを作成した上でカテゴリー分けするといいでしょう。
反対に、膨大な量のコンテンツがある場合は、細分化した階層構造にすることで、目的のページに素早く辿り着けるようになります。
7. 関連する記事を内部リンクでつなげる
同じカテゴリー内にあるページ同士は、ページ内に内部リンクを設置することでより多くのユーザーが記事を見やすく、疑問を解消しやすくなります。
たとえば、Webマーケティングに関する解説を行ったページには、「離脱率」「CVR」「企業SNS」などについて書かれているページにつなげます。
各ページに対して内部リンクを設定することで、ユーザーは記事に対してより理解を深めやすくなり、回遊性や滞在時間の向上が期待できるでしょう。
カテゴリー分けを行った後にやるべきこと
カテゴリー分けを行ったら、カテゴリーのトップページを作成します。
とくに、コンテンツ量が多いサイトや、商品数の多いECサイトの場合は、カテゴリー検索を行うことが多いため、トップページの作成は必須です。
カテゴリーのトップページを作成したら、それぞれのカテゴリーをサイトのグローバルメニューやフッターに設定しましょう。
カテゴリーを設定しただけでは、ユーザーが気づかず利用してもらえない可能性があります。サイト内に設置するまでがカテゴリー分けの作業です。
カテゴリに沿って記事作成を進める際の注意点
分類したカテゴリに沿って記事作成を進める際の注意点としては、次の二つが挙げられます。
はじめのうちはひとつのカテゴリだけに注力して記事数を増やすこと
1記事に設定するカテゴリを制限すること
はじめのうちはひとつのカテゴリだけに注力して記事数を増やすこと
同時に複数のカテゴリの記事を作らない理由は、サイトの専門性を手早く高めるためです。カテゴリが5つあったとして、5つのカテゴリをバランスよく記事作成すると、検索エンジンからすると「何をテーマに取り扱っているサイトなのか」の理解に時間がかかってしまい、サイト全体が評価されるタイミングが遅れてしまいます。
そこでサイト設計時に検討したカテゴリの中で優先度を決めて、ひとつずつカテゴリを完成させていくイメージで進みましょう。
1記事に設定するカテゴリーの制限
1つの記事に対して複数のカテゴリーを設定する場合、適切な制限を設けましょう。記事に過剰なカテゴリーを設定すると、ユーザーが迷ってしまうだけでなく、検索エンジンが正確な評価を行いにくくなることがあります。1つの記事に対して2つまで、多くても3つのカテゴリーを設定までがおすすめです。
カテゴリー分けに関するよくある質問
ここからは、カテゴリー分けに関するよくある質問に回答します。
カテゴリー分けは必ずするべき?
カテゴリー分けは、絶対にするべきというわけではありません。記事数やページ数が少ない場合などは、カテゴリーがなくても問題ないでしょう。
しかし、記事やページが増えるにつれ、コンテンツの整理が難しくなるので、基本的にはカテゴリー分けをしてサイト内を整理することが重要です。
カテゴリーの数はどのくらいが最適?
カテゴリーの数は、サイトの規模やテーマなどによって異なります。そのため、一概におすすめする数はありません。
ただし、あまり細かくカテゴリー分けするとユーザーが記事を探しづらくなってしまう可能性もあるので注意が必要です。
カテゴリー分けに役立つツールは?
カテゴリー分けを行う前には、キーワード選定ツールが役立ちます。Googleのキーワードプランナーやラッコキーワードを活用することで、関連キーワードや検索ボリュームを出すことができます。
カテゴリの分類方法で困ったらLeadGridまでご相談ください
この記事ではカテゴリ分けのSEOへの影響や手法について紹介しました。3つのコツも解説したので、この記事を参考にカテゴリ分けを行ってみましょう。
もし「カテゴリの分類も、そもそもキーワード選定も複雑で難しい」場合は、LeadGridチームまでご相談ください。綿密なヒアリングの元、貴社のサイトに適切なキーワードをカテゴリとともにご提案します。

またLeadGridは株式会社GIGがWebサイト制作の際に使用する、ブログ機能の使い勝手の良さが評判のCMSです。「ブログサービスのような使い勝手でわかりやすい」と導入の企業様からお声をいただくことも多く、良質なコンテンツの制作に集中しやすいCMSと言えます。
キーワード選定やカテゴリの分類はSEOの重要な役割を占めますが、もちろん記事コンテンツそのものの質も、とても重要です。使いやすいCMSで、貴社の知見やノウハウを読者にとってわかりやすく発信するサポートをいたします。
今すぐ試せる、CVR改善リストを無料配布中!
CVRを今すぐ改善したい担当者様へ。業界別のCVR平均値をもとに、CVR改善ポイントを15個リストアップした資料をご用意しました。この後の業務からぜひご活用ください。
LeadGrid BLOG編集部は、Web制作とデジタルマーケティングの最前線で活躍するプロフェッショナル集団です。Webの専門知識がない企業の担当者にも分かりやすく、実践的な情報を発信いたします。
関連記事
-

ホームページの問い合わせを増やすには?フォームの作り方から改善策まで解説
- # Webマーケティング
- # Webサイト
-

Web集客が得意な代行会社7選|選び方やメリット・デメリットを紹介
- # Webマーケティング
-
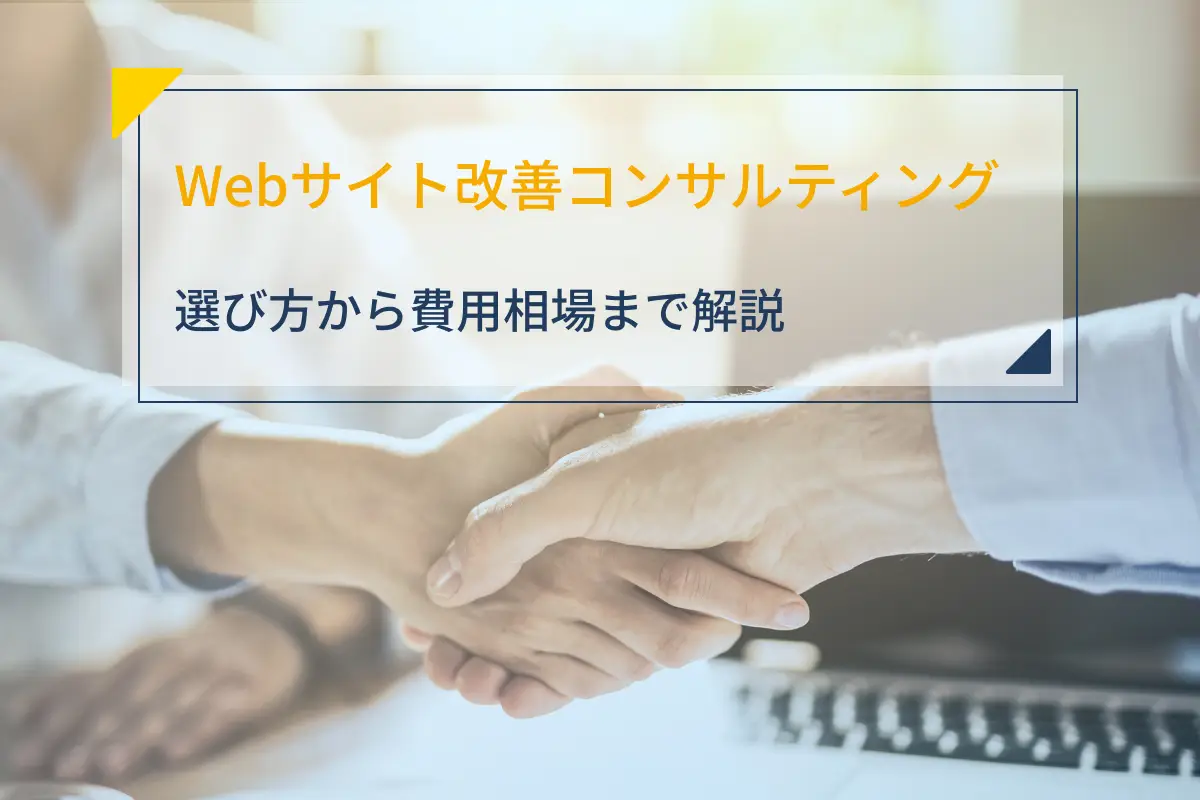
Webサイト改善コンサルティング10選!選び方から費用相場まで解説
- # Webマーケティング
- # Webサイト
-

SNS運用代行とは?依頼できる内容やメリット・おすすめの会社を紹介
- # Webマーケティング
-

TikTok採用とは?メリット・デメリットや成功事例を詳しく解説
- # 採用サイト
-

【比較表付き】MAツールおすすめ13選!選び方や主な機能についても解説
- # Webマーケティング
- # MAツール
Interview
お客様の声
-
SEO・更新性・訴求力の課題を同時に解決するため、リブランディングとCMS導入でサービスサイトを刷新した事例
ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社 様
- # サービスサイト
- # 問い合わせ増加
- # 更新性向上
 Check
Check -
「SEOに閉じないグロースパートナー」へ想起転換したコーポレートサイト刷新の事例
株式会社LANY 様
- # コーポレートサイト
- # リブランディング
- # 採用強化
 Check
Check -
企業のバリューを体現するデザインとCMS刷新で情報発信基盤を強化。期待を超えるサイト構築を実現した事例
株式会社エスネットワークス 様
- # コーポレートサイト
- # 更新性向上
 Check
Check -
採用力強化を目的に更新性の高いCMSを導入し、自社で自由に情報発信できる体制を実現した事例
株式会社ボルテックス 様
- # 採用サイト
- # 採用強化
- # 更新性向上
 Check
Check
Works