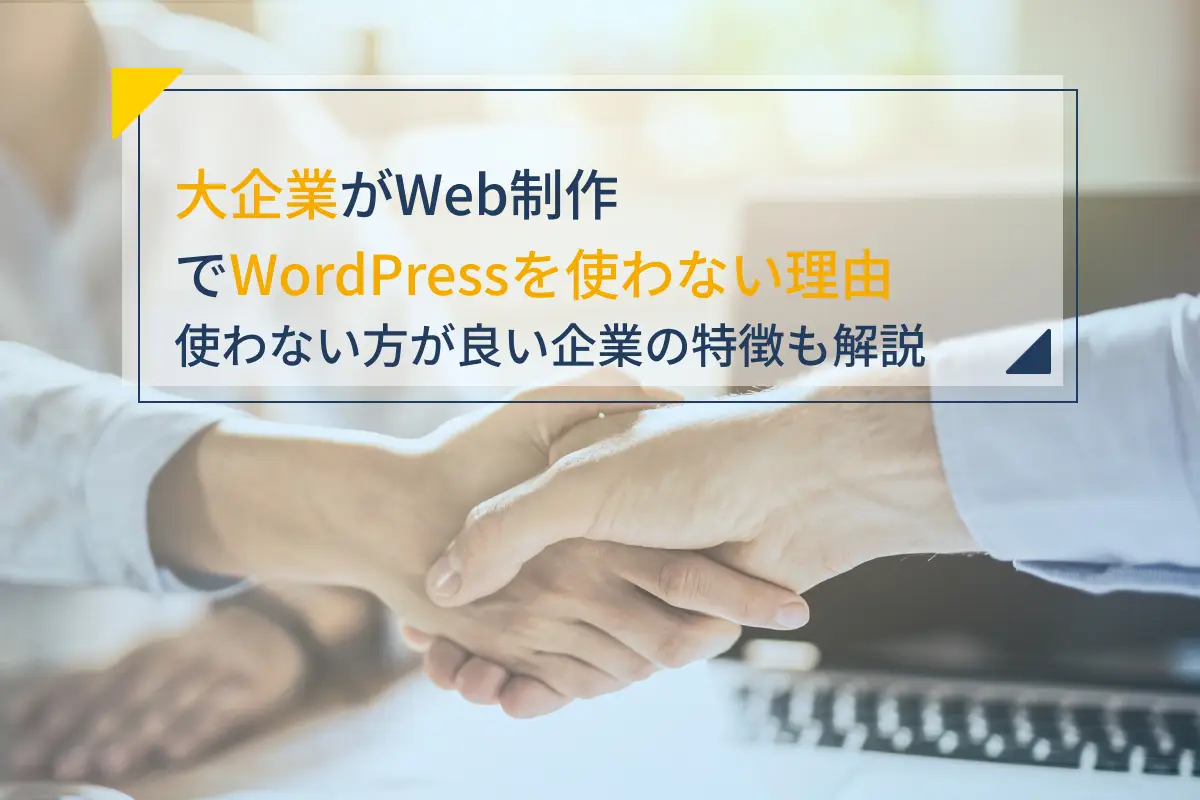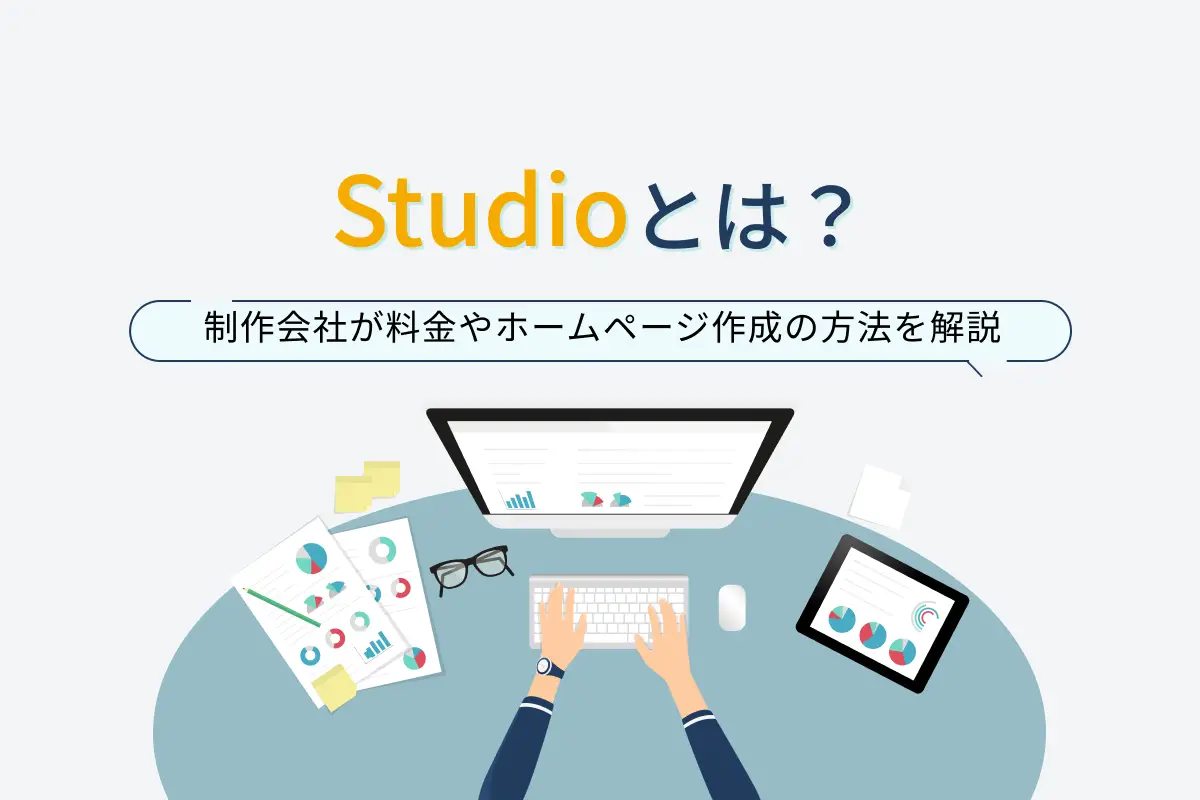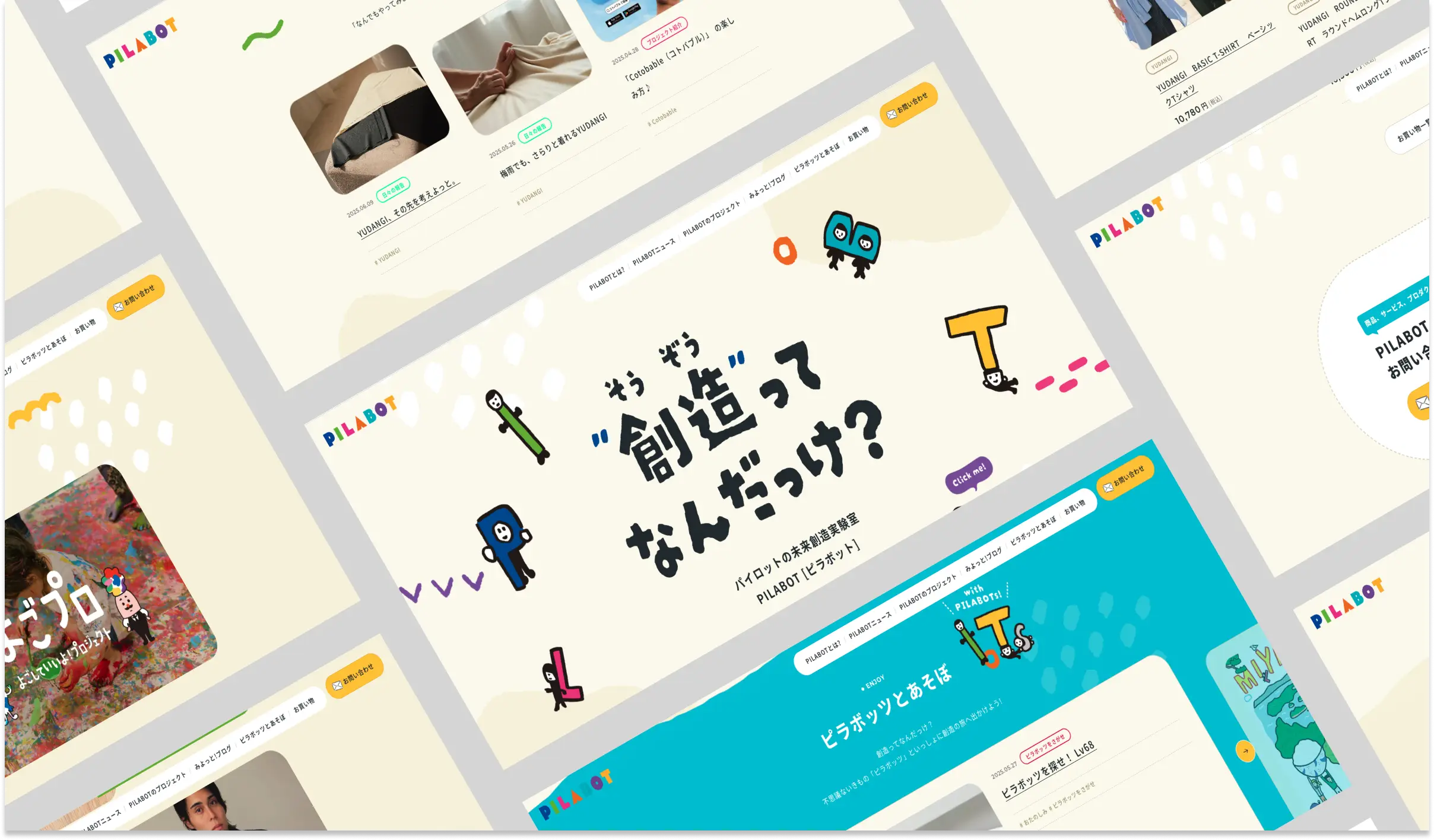CRM運用を成功させるポイントは?導入のメリットや失敗の原因についても解説
CRM運用を成功させるポイントは?導入のメリットや失敗の原因についても解説
デジタルマーケティングツール比較ガイド、無料配布中!
国内で有名なCMS・MA・CRM/SFA、その他解析ツールを一つの資料にまとめた人気の資料を無料でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください。
CRM運用は、企業が顧客との関係を深め、収益向上を実現するための鍵となる重要な取り組みです。特にデジタル化が進む昨今では、顧客データの一元管理や効果的な活用が収益面で大きな差を生むようになりました。
ただし「システムを導入すれば自然に成果が出る」と、思い込むのは避けましょう。運用の方向性を誤ると、せっかくのCRMツールが入力の手間だけを増やす無用の長物となりかねません。
本記事では、CRMの基本から運用のポイントまでを詳しく解説します。自社の顧客管理やマーケティングを強化し、効率良く成果を高めたい方はぜひ最後までご覧ください。
CRMとは
CRM(顧客関係管理)は「Customer Relationship Management」の略です。顧客データを中心に営業・マーケティング・サポートを最適化し、長期的な顧客ロイヤルティ向上を目指す概念を指します。
現代ではクラウド型の顧客管理システムを用いることが多く、受注情報や問い合わせ内容などを一元管理することで、組織として顧客の状況を常に把握できる点が特徴です。
CRMの運用が求められる理由として、以下のような背景が挙げられます。
- 新規顧客獲得のハードル上昇
- 顧客ニーズの多様化
- データ利活用による業務効率化・コスト削減
特にコロナ禍以降、新規市場を開拓することが難しくなり、既存顧客との関係を深めることが企業存続の要になりました。既存顧客を満足させる施策が成長の原動力になるといわれるのも、こうした社会背景があるためです。
また、CRM運用は業務効率化の手段としても重宝されます。アナログな営業活動では、担当者が変わるたびに顧客情報が散在し、引き継ぎに手間取ることがしばしば。しかしCRMシステムに入力された情報を活用すれば、担当者が変更になったとしてもスムーズに顧客対応を続けられます。情報の属人化を防ぐ点は、CRM導入の大きなメリットといえます。
関連記事:顧客管理(CRM)とは?重要性やシステム導入のメリット、選ぶポイントを解説
CRM運用のメリット
実際にCRMを使いこなすとどのような恩恵があるのでしょうか。大きく分けて以下のメリットが挙げられます。
- 顧客満足度とLTV向上
- 業務効率化と属人化の解消
- データドリブンな戦略立案が可能
顧客満足度とLTV向上
CRMを導入し運用が軌道に乗ると、顧客視点のサービス改善ができるようになります。顧客情報を基点に課題や要望を把握することで、ピンポイントなフォローや商品提案が可能になるためです。顧客との接点をきめ細かく設けることにより、短期的なリピートだけでなく、長期的なファン化へとつなげやすくなります。
特にサブスクリプション型のビジネスでは、継続率の向上が収益に直結するため、顧客満足度の向上は極めて重要です。つまり CRM運用の徹底で実現する満足度の高さが、LTV(顧客生涯価値)拡大の大きな鍵となります。
業務効率化と属人化の解消
CRMに顧客情報を集約すれば、営業やサポートの担当者がいつでも必要なデータへアクセス可能になります。商談履歴や問い合わせ履歴を体系的に把握できるため、重複対応やヒアリング不足のような無駄な動きが格段に減ります。
またベテランの営業担当者が築いた関係性をシステム上に共有することで、人材異動や退職によるデータ損失リスクを大きく軽減できる点もメリットです。特に定型業務のスピードアップが期待できるので、コア業務へ注力できる環境を作り出せます。
データドリブンな戦略立案が可能
従来の営業活動やマーケティング施策は、属人的な経験や勘に頼る部分が大きい傾向にありました。しかしCRMを導入することで、受注確度や購買履歴、問い合わせ傾向など「データに基づく戦略」を容易に打ち出せるようになるため、戦術精度の向上や費用対効果の改善が期待できます。
特にSFA(Sales Force Automation)やMA(Marketing Automation)と連携させることで、より詳細なデータ取得や施策実行が行えます。CRM運用を軸にデジタルツールを組み合わせることで、顧客アプローチ全体を最適化する流れが近年のトレンドです。
CRM運用が失敗する原因
CRMシステムは便利ですが、導入しただけで確実に成果が出るようなものではありません。それどころか、現場の実情に合わせた仕組みを作らないと、運用の手間だけが増えて挫折するケースもあります。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 運用目的があいまいで現場が疲弊してしまう
- 入力ルールが複雑すぎる
- 効果がすぐ出ると期待しすぎる
- データの質が低く分析に活かせない
運用目的があいまいで現場が疲弊してしまう
「なんとなく顧客情報を集めたい」などという曖昧な理由で導入したものの、具体的な目標や活用シナリオが固まっていないと、入力作業の意義を現場が感じられません。それによって入力を怠るメンバーが増え、システムが形骸化する恐れがあります。
よくあるのは「顧客データベースを整備して満足」してしまうパターンです。 CRM導入の先に何を実現するかを明確に提示しない限り、熱意ある運用は続かないと考えられます。
入力ルールが複雑すぎる
現場のスタッフは、日々の営業やサポート業務だけでも多忙です。そこに煩雑な入力ルールやカスタム項目が多すぎると、「システム管理が本業」という状況になりかねません。入力工数を最小限に抑えられないと、メンバーの負担が大きくなり運用ストップの原因になります。
最低限の必須項目を決めて、簡潔なフォーマットで進めることを優先しましょう。例えば、部署名や担当者名といった、入力しなくても実務に影響が少ない項目は削減するなど。シンプルにすることを心がけましょう。
効果がすぐ出ると期待しすぎる
CRM運用による成果は中長期的に現れるケースが大半です。顧客ロイヤルティ向上やリピート率改善といった指標は、数週間単位で大きく動くものではありません。短期間で数値改善が見えないからといって焦り、運用の手を止めてしまうのは危険です。
数か月~半年スパンでデータ蓄積と分析を続け、継続的にアクションを改善する姿勢が大切です。「腰を据えて顧客情報と向き合う」意識を組織全体で共有しておきましょう。
データの質が低く分析に活かせない
せっかくCRMに入力しても、記載ミスや重複、更新漏れが多く、実態を反映していないケースは珍しくありません。誤った顧客情報をもとに施策を行うと逆効果になるため、データ品質の管理に注意しましょう。
名寄せルールの統一や入力ガイドラインの作成は、初期段階から取り組みたい要素です。ポイントは、「こう書かなければいけない」ではなく、できるだけ書きやすい形に整備すること。現場へのヒアリングを通じて、管理しやすい項目や入力方法を検討しておくとよいでしょう。
CRMシステムを使った運用の流れ
効果的にCRM運用を行うためには、単にシステムを導入するだけでなく「どう活用するか」という面での準備が欠かせません。以下のプロセスに沿って取り組むとスムーズです。
1.運用目標と評価指標を定める
まずはCRMを通じて具体的に何を達成するのか、数字ベースで目標を明確化しましょう。例としては下記のような指標があります。
- 問い合わせ数を前月比で何パーセント増やすか
- 継続率またはリピート率を何パーセントに高めたいか
- 新規顧客獲得コスト(CAC)をどの程度削減したいか
評価指標をKPIとして設定し、毎月または四半期ごとにモニタリングしていきます。関係者全員が共通のゴールを認識していれば、入力へのモチベーションも自然と高まります。
2.入力負荷をできるだけ軽減する
システムへの入力が煩雑だと、現場が「運用しにくい」というイメージを強く持つようになり、放置につながるリスクがあります。実装時には下記を検討してください。
- 自動取得できるデータを増やす(名刺管理ツールやフォーム連携など)
- 必須項目をできるだけ厳選する
- 入力ミスを減らす選択式や定型フォーマットを活用する
特に連携ツールを増やして入力補助をする方法は有効です。営業やカスタマーサポートが、極力手動入力しなくて済むようなフローを検討しましょう。
3.分析したデータを具体的な施策に落とし込む
データ収集だけに終始してしまうと、CRM運用の成果を十分に得られません。分析結果をもとに、顧客セグメント別の施策やアプローチを決定するなど、実行プランを作成しましょう。
例えば以下のような活動です。
- 離脱率が高い顧客層に対して、メールや電話でフォローを徹底する
- 購買頻度が高い層を「上位顧客」と位置付け、限定特典を提供して満足度をさらに高める
- 新規リードに対してMAツールでシナリオ配信し、商談化を促す
CRMが提供するダッシュボードやレポート機能を活かし、客観的に課題を見つけ、具体的な対処策を反映していくことが重要です。
4.運用ルールの定期的な見直し
一度運用ルールを決めたとしても、運用している過程で実態とのズレが出てきたり、新たな課題が見つかったりする可能性があります。四半期や半年ごとにルールを見直し、入力項目の追加・削除やマニュアルの改訂を行うのがおすすめです。
現場メンバーへのアンケートを実施し、「どの工程が面倒」「どこにメリットを感じる」といった生の声を把握するのも有効です。常に使いやすい環境を作ることが、長期運用の成功を支えます。
CRM運用を成功させるポイント
CRM運用を成功させるには、運用を現場に定着させ、組織全体で顧客情報を共有する土台を作ることが大切です。ここからは、運用をスムーズに根付かせるため、下記のポイントをさらに掘り下げます。
- 全社的な意識づけを強化する
- データ入力と更新のタイミングを明確化する
- 顧客セグメントに応じた施策を立案する
- 定期的な研修やナレッジ共有を行う
全社的な意識づけを強化する
CRM運用は営業やサポートなど特定部門に閉じた取り組みではありません。マーケティングや商品企画、経営層も同じプラットフォームで顧客の声を拾うことで、横断的な意思決定が行いやすくなります。
全社的な活用を促すためには、トップやマネージャーのコミットメントが不可欠です。導入メリットや目標を共有し、運用ルールに従うことが会社として必須であるとの認識を広めましょう。
データ入力と更新のタイミングを明確化する
いつ、どのタイミングで誰が入力するかといったルールが曖昧だと、「確認したら情報が古い」「誰も更新していない」という事態を招きます。そういった事態を防ぐため、下記のようなルールを設定するのがおすすめです。
- 商談が終了したら、24時間以内に担当営業が入力する
- 問い合わせ対応後、にサポート担当が翌日までに更新する
- 毎週金曜日に、各チームリーダーがデータの整合性をチェックする
こうした具体的な締め切りを設けると、入力の滞りを防止できます。あわせて「入力の手間とメリットのバランス」を考慮しながら、現場の負荷が過剰にならない設定を心がけるようにしましょう。
顧客セグメントに応じた施策を立案する
CRM運用の目的の一つは、顧客を適切にセグメント化し、それぞれに最適な施策を届けることです。以下の要素で分類すると効果的でしょう。
- 購買頻度・利用回数
- 顧客の業種・規模
- 問い合わせ件数・履歴
- 契約プラン・契約期間
特にBtoBでは企業ごとに業界課題が異なるため、セグメントに合わせたメールマーケティングやキャンペーン告知などを工夫すると成果が高まりやすいです。CRMが整ったら必ず顧客分析を行い、セグメント別施策を検討しましょう。
定期的な研修やナレッジ共有を行う
「システムを入れたものの、現場の担当者に操作方法が浸透していない」というケースもあります。それを防ぐために、担当者を集めた勉強会やオンラインマニュアルの整備を行い、誰でも基本操作が分かるようにしておきましょう。
また、成功事例や改善につながった取り組みは社内に共有し、良い実践を横展開する文化を醸成すると、CRM運用の成熟度が上がります。ツールを使いこなす「運用リーダー」を各部署に配置してサポートする形も有効です。
CRMシステムを選ぶ基準
CRM運用で成功するには、システム選定が重要です。多種多様な製品がある中で、自社に最適なものを見極める基準を押さえておきましょう。
関連記事:【2025年】CRMツールおすすめ10製品を比較|機能や選び方についても
目的と利用部門
システム導入にあたっては、まず「営業改革が目的なのか」「カスタマーサクセス強化なのか」「複数部門にわたる統合管理なのか」など、狙いを定めておくことが重要です。小規模で営業チームのみ使うのであればシンプルな機能で十分な場合がありますが、全社利用を想定するなら権限設定や拡張性が重視されるでしょう。
利用部門によって必要機能が変わります。サポート部門が使うなら問い合わせ管理やチケット管理が重視される一方で、マーケティング担当はメール配信やMA連携を重視するかもしれません。部門の要望をヒアリングしながら要件定義するステップを、省かないことが大切です。
使いやすさとサポート体制
特に導入初期は、現場が操作方法に戸惑いがちです。日本語マニュアルや研修、電話・チャットによるサポートなどがあると安心です。サポートの迅速さや柔軟性は、長く使ううえで大きなメリットとなるでしょう。
またUIの分かりやすさも重要です。実際にデモを試してみて、直感的にデータ入力ができるか、視認性や検索機能が良好かを確認してください。使い勝手が悪いと、せっかくシステムを導入してもユーザー定着率が低迷します。
必要機能と拡張性
例えば下記のような機能を、どの程度重視するか事前に洗い出しましょう。
- SFA(営業支援)との連携や案件管理
- MA(マーケティングオートメーション)とのシームレス連携
- 問い合わせ管理・チケット管理
- 外部サービス(会計システムやBIツール)とのAPI連携
- カスタム項目の追加や独自ワークフロー構築
一度導入すると変更や乗り換えは手間がかかります。将来の事業拡大や新規部門導入を踏まえて拡張性やカスタマイズ性がどの程度あるかも確認しましょう。
CRM活用と併用したい施策
CRM運用で顧客情報が整理されると、さまざまな施策との連携が進めやすくなります。ここではCRMと相性のよい取り組みを挙げてみましょう。
関連記事:MAツールとSFA/CRMの違いとは?連携するメリットも解説
MAツールとの統合
見込み顧客を段階的に育成するには、MA(Marketing Automation)の活用が有効です。メールやWeb行動履歴をスコアリングし、スコアが一定以上になったら営業へ自動でアラートを出す、といった仕組みが実現できます。CRMに集積された顧客データをもとに、潜在顧客への最適なアプローチを自動化できるメリットは大きいです。
SFA(営業支援システム)との連携
すでにSFAを利用している場合、CRMとの連携を強化すれば商談管理から受注後のサポート体制まで一気通貫で管理可能になります。「見込み客」「既存客」という区分にとらわれない全社的な顧客支援を進めるために、SFAとCRMの連携を深める例は多いです。
顧客成功(CS)活動での活用
カスタマーサクセスの考え方が浸透しており、特にサブスクリプション型ビジネスでは顧客の継続利用が収益を左右します。サポート履歴や利用状況をCRMで管理すれば、「利用が減っている顧客には追加サポートを提案する」「高度な機能を活用中の顧客には上位プランを案内する」など柔軟に対策できます。
分析プラットフォームとの連携
BIツールやデータウェアハウスと連携させることで、CRMのデータをさらに高度な視点で分析できます。顧客の離脱要因やLTVに影響を与える要素を可視化し、製品開発や経営戦略へ落とし込む動きが近年注目されています。
CRM運用に悩んだらWebサイト整備も同時に検討しよう
ここまでCRM運用のメリットや失敗原因、成功させるためのポイントを幅広く紹介しました。しかし、顧客データを活用して成果を高めるには、Webサイト側の仕組みやマーケティング施策も同時に最適化する必要があります。
もしWebサイトが古く、問い合わせ導線が分かりにくい場合は、CRM導入に併せてサイトリニューアルを検討すると良いでしょう。Webサイト=顧客接点を強化するほど、CRMにも質の高いデータが集まりやすくなります。

もしCRM運用の成果を最大化するためにWebサイトを整備したい、顧客接点を増やしたいとお考えなら、LeadGridを検討してみるのはいかがでしょうか。BtoBに強い設計が施されており、クラウド型なので運用の手間を大幅に削減できます。サポート体制も充実しているため、初めての方でも安心です。
LeadGridの詳細や導入相談はこちらから可能です。CRM運用とWebサイトの一体化で、顧客対応とリード獲得をさらに高い次元へ引き上げましょう。

デジタルマーケティングツール比較ガイド、無料配布中!
国内で有名なCMS・MA・CRM/SFA、その他解析ツールを一つの資料にまとめた人気の資料を無料でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください。
LeadGrid BLOG編集部は、Web制作とデジタルマーケティングの最前線で活躍するプロフェッショナル集団です。Webの専門知識がない企業の担当者にも分かりやすく、実践的な情報を発信いたします。
関連記事
Interview
お客様の声
-
SEO・更新性・訴求力の課題を同時に解決するため、リブランディングとCMS導入でサービスサイトを刷新した事例
ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社 様
- # サービスサイト
- # 問い合わせ増加
- # 更新性向上
 Check
Check -
「SEOに閉じないグロースパートナー」へ想起転換したコーポレートサイト刷新の事例
株式会社LANY 様
- # コーポレートサイト
- # リブランディング
- # 採用強化
 Check
Check -
企業のバリューを体現するデザインとCMS刷新で情報発信基盤を強化。期待を超えるサイト構築を実現した事例
株式会社エスネットワークス 様
- # コーポレートサイト
- # 更新性向上
 Check
Check -
採用力強化を目的に更新性の高いCMSを導入し、自社で自由に情報発信できる体制を実現した事例
株式会社ボルテックス 様
- # 採用サイト
- # 採用強化
- # 更新性向上
 Check
Check
Works