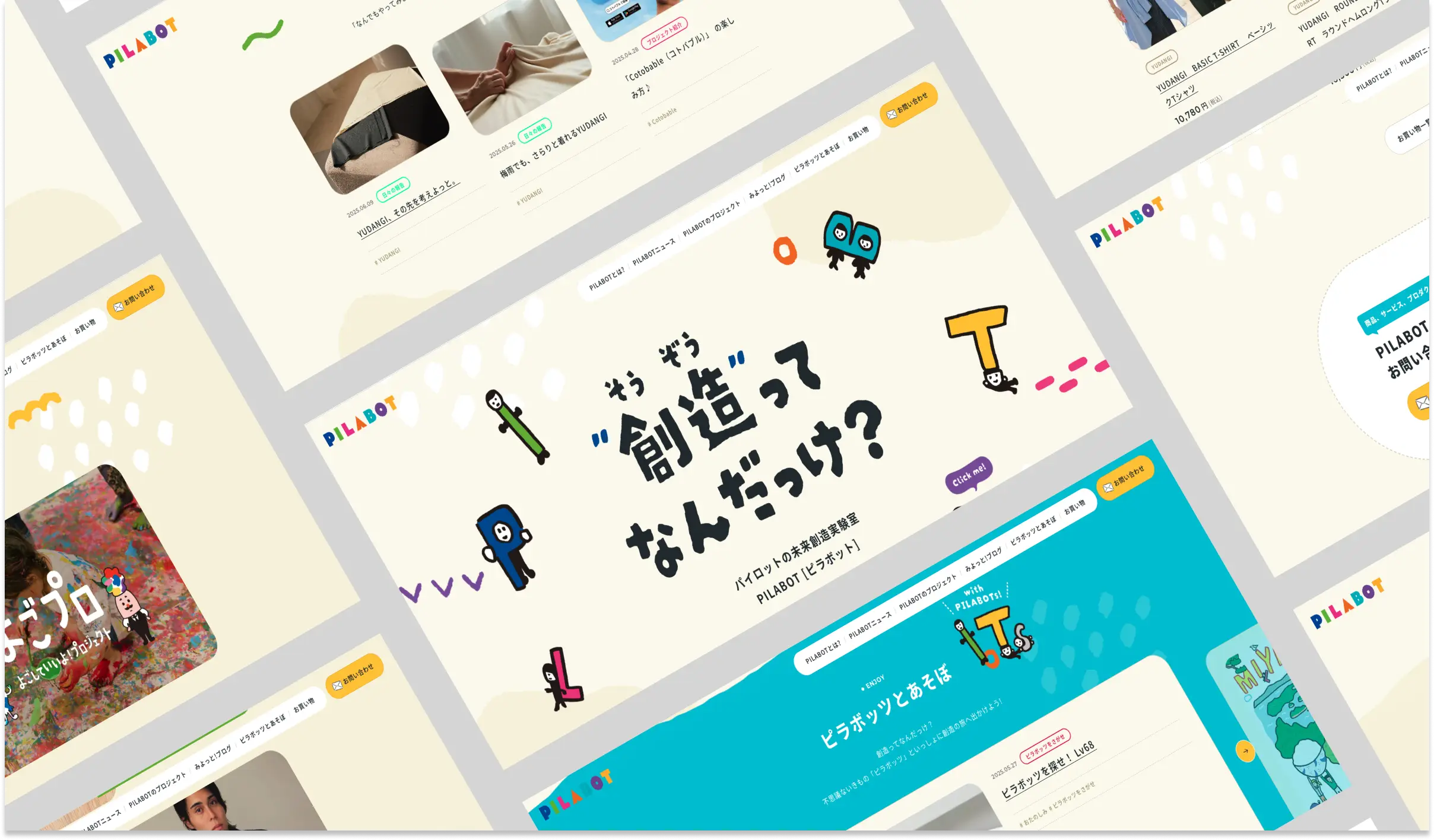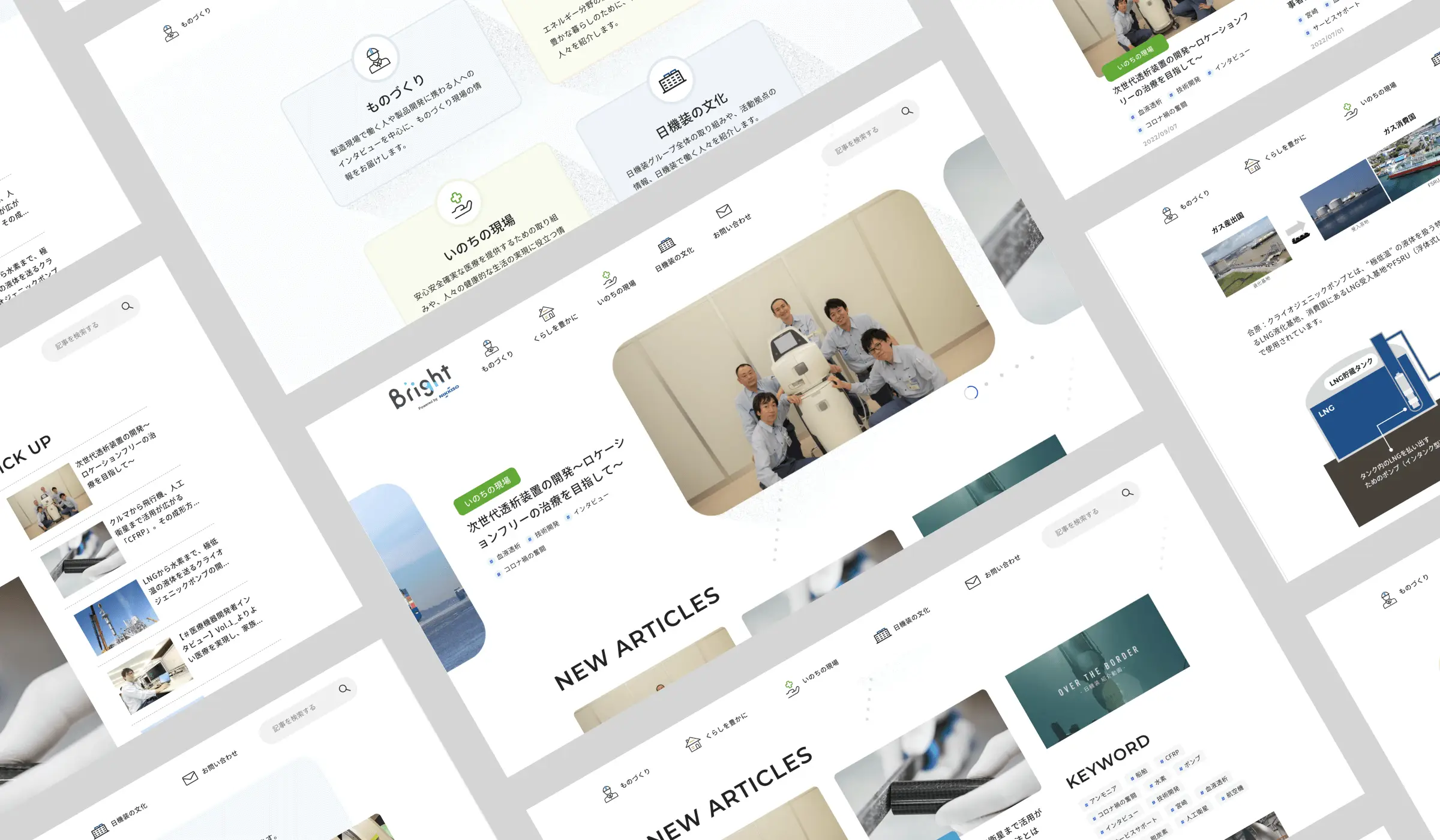オウンドメディアとは|運用する目的や活用事例、作り方とコツも解説
オウンドメディアとは|運用する目的や活用事例、作り方とコツも解説
予算別でわかる!
オウンドメディア制作事例集、無料配布中!
各企業の予算に応じた制作事例を一挙公開。オウンドメディア依頼前に費用相場を把握し、自社に最適なサイトを構築するためのアイデアやヒントが満載の資料を無料でダウンロードできます。ぜひご活用ください!
マーケティング手法として主流になったオウンドメディア。
オウンドメディアは商品やサービスの認知拡大、企業のブランディング、採用活動など幅広いシーンで活用されています。
しかし「企業ホームページと別に運営するメリットがわからない」「SNSだけではダメなのか」と疑問に感じる経営者・Web担当の方も多いのではないでしょうか。
この記事ではオウンドメディアと企業ホームページやSNSとの違い、オウンドメディアを作る目的、メリットとデメリットを解説します。
オウンドメディアを作る流れや失敗しないコツも紹介しますので、オウンドメディアの立ち上げにお役立てください。
オウンドメディアとは情報発信を行う自社保有のメディアのこと
オウンドメディア(Owned Media)は、その名の通り自社で所有(owned)するメディアのことです。
広い意味では企業ホームページやメールマガジン、紙のパンフレットなどもオウンドメディアに入ります。
ただデジタルマーケティングの世界では、おもに自社ブログのような「企業がユーザーへ情報発信を行うWebサイト」に限定して使われます。
オウンドメディアとホームページ・公式サイトとの違い
オウンドメディアと企業のホームページ・公式サイトの違いは、それぞれの目的にあります。
たとえば、ホームページの目的は、企業情報の発信やブランディング、求職者に対する採用活動などさまざまです。対してオウンドメディアは、主に「マーケティング」を目的としています。
オウンドメディアと企業ホームページ(コーポレートサイト)は「目的」「ターゲット(想定読者)」「掲載内容」に下記のような違いがあります。
オウンドメディア | ホームページ | |
目的 | マーケティング | 企業の紹介と信頼獲得 |
ターゲット (想定読者) | 潜在顧客を含む不特定多数 |
|
掲載内容の例 |
|
|
ホームページは、すでに自社を認知している相手に向けて企業が自社を紹介するためのWebサイトです。よって「どこで何をしている会社か」がわかる情報を掲載します。
一方、オウンドメディアのターゲットには自社をまったく知らない潜在顧客も含まれます。そのため掲載内容も、自社の商品やサービスの魅力に気づいてもらえる情報がメイン。自社紹介は必須ではありません。
ホームページは「企業の紹介と信頼獲得」、オウンドメディアは「マーケティング」と役割が異なるため、ホームページに加えてオウンドメディアを制作する企業が増えています。
BtoBの場合は、オウンドメディアに自社商材に関する資料請求や問い合わせなどのCTAを設けて商談化を狙うことが多く、見込み顧客の増加につなげることが可能です。
オウンドメディアの目的5つ
企業がオウンドメディアを運営する目的は次の5つがあげられます。
認知拡大し、初回接触を狙うため
ブランディングのため
顧客ロイヤルティ(愛着)を高めるため
リード獲得のため
採用強化のため
認知拡大し、初回接触を狙うため
オウンドメディア内で顧客に対して有益な情報発信をすることで、自社を知らない潜在層に認知してもらえるようになります。
オウンドメディアでは自社の商品やサービスだけではなく、想定顧客にとって有益な情報を発信していくことが多いです。有益な情報の発信は、SEO評価を上げることにもつながり、潜在層へリーチしやすくなります。
つまり、有益な情報発信により検索上位表示されたオウンドメディアは、能動的に検索をおこなう潜在層の流入を獲得できます。そして、メディア内のコンテンツを通して商品やサービスを知ってもらう機会が増え、営業の効率化も図れます。
このような潜在層への認知拡大が、オウンドメディア運用目的の一つ目となります。
ブランディングのため
自社のブランディングを目的にオウンドメディアを活用する企業も少なくありません。
オウンドメディアに掲載される情報は企業イメージに直結します。高品質で有益なコンテンツはオウンドメディアに対するユーザーの信頼獲得、ひいてはそのメディアを運営している企業のイメージアップにつながります。
つまり良質なオウンドメディアは、自社や商品・サービスのファン育成に役立つわけです。
オウンドメディアを使ったブランディング方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:オウンドメディアでブランディングは可能?メリットを徹底解説
また会社のオフィス紹介や先輩社員のインタビューなどをオウンドメディアに載せることで、採用活動にも展開できます。
オウンドメディアを使ったリクルーティングについてはこちらの記事をどうぞ。
関連記事:オウンドメディアリクルーティングとは?メリットや手順など
顧客ロイヤルティ(愛着)を高めるため
顧客ロイヤルティ(愛着)を高める目的でオウンドメディアを運営する企業も存在します。
オウンドメディアにアクセスするユーザーは、新規顧客だけではありません。商品・サービスをすでに利用している既存顧客に向けたコンテンツを用意することで、顧客ロイヤルティを高められるでしょう。
具体的には、商品・サービスに込められた思いや、リリースまでの裏側などをまとめたコンテンツが有効です。これらの情報を提供することで「この商品を選んでよかった」と感じてもらいやすくなります。
リード獲得のため
オウンドメディアはリード(見込み客)獲得に役立ちます。
なぜならオウンドメディアは、そのコンテンツの内容に関連した悩みや疑問を抱えているユーザーがアクセスするためです。よって 「解決方法」として自社の商品やサービスをアプローチすれば、関心を持ってもらいやすいのです。
例えば、LeadGridのようなリード獲得に特化したCMSを使用すれば、手間のかかる問い合わせフォーム作成や資料(ホワイトペーパー)のダウンロード設定も簡単に行なえます。
「自社オウンドメディアに合ったCMSがどれか分からない」という方は、無料配布資料「CMS比較一覧表」をぜひ参考にしてみてください。フォーム管理や資料管理などの機能に加え、マーケティング支援などのサポートの観点などからも比較しているため、自社にとって必要な機能をひとめで確認できます。
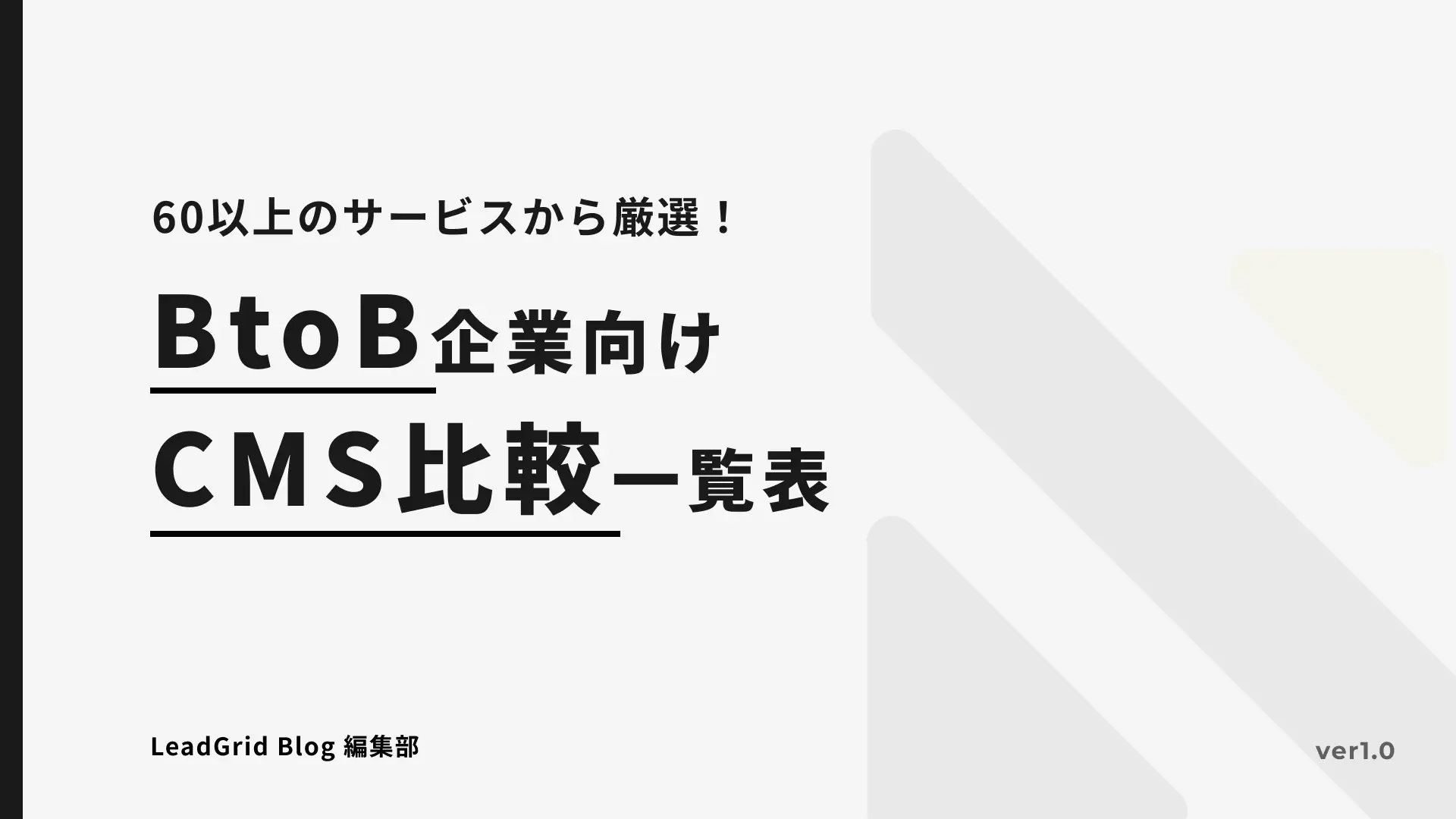
オウンドメディアのマーケティング活用についてはこちらの記事でより詳しく解説しています。
関連記事:オウンドメディアマーケティングとは?注目される理由やコツ
採用強化のため
オウンドメディアは採用強化の目的でも利用されます。掲載できる情報が限られている求人サイトとは違い、オウンドメディアでは自由に情報を発信できる点が魅力です。
会社とのミスマッチを減らした上で優秀な人材を獲得するための採用広報と、オウンドメディアの相性は良いです。社員インタビューや会社の魅力、社内行事など会社のリアルな姿の発信が効果的です。
採用オウンドメディアで継続的な情報発信をすることで、潜在的な転職希望者への認知拡大も可能です。このような潜在層へリーチすることで、すぐには転職をしなくても、転職時に選ばれやすい会社になります。
このように、求める人材と出会うために役立つサイト制作のフローやポイントは無料配布資料「採用サイトのつくりかた」に掲載しています。成功事例と自社を比較しながら、オウンドメディアにおける戦略に役立ててみてください。
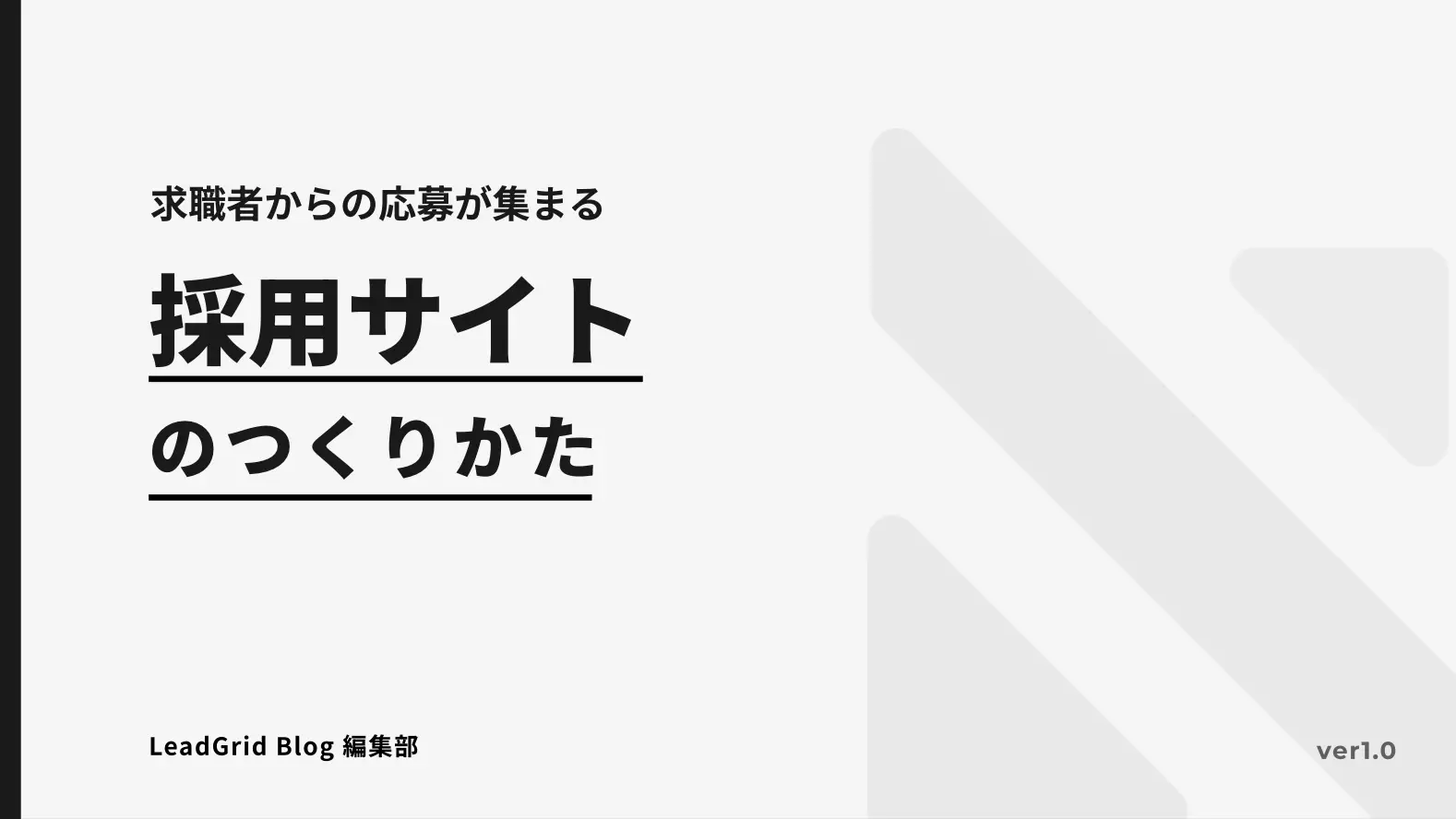
オウンドメディアを運用する4つのメリット
オウンドメディアのメリットは次の4つです。
自然検索からの流入経路を確保でき、広告費を削減できる
SNS施策(アーンドメディア)や広告施策(ペイドメディア)との掛け合わせでより成果を創出できる
コンテンツが資産になる
コンテンツを二次利用できる
自然検索からの流入経路を確保でき、広告費を削減できる
オウンドメディアは自然検索からの流入経路を確保できるため、広告費を削減できるメリットがあります。
SEO施策は効果が出るまでに時間と手間がかかるものの、うまくいけば無料の集客手段となるでしょう。広告を出稿しなくても、サイトへのまとまった流入を見込めるようになるため、広告費の削減につながります。
Web広告の相場は月額10~50万円といわれているため、広告に頼らないオウンドメディアでの集客は企業にとって魅力的な施策です。
SEOに関するリソースがなく、何から着手すれば良いか分からない方は無料配布資料「初期段階の内部SEO」のチェックシートを活用して見ることをおすすめします。現状メディアに不足している要素を洗い出すことで、施策の方針が見えてくるかもしれません。
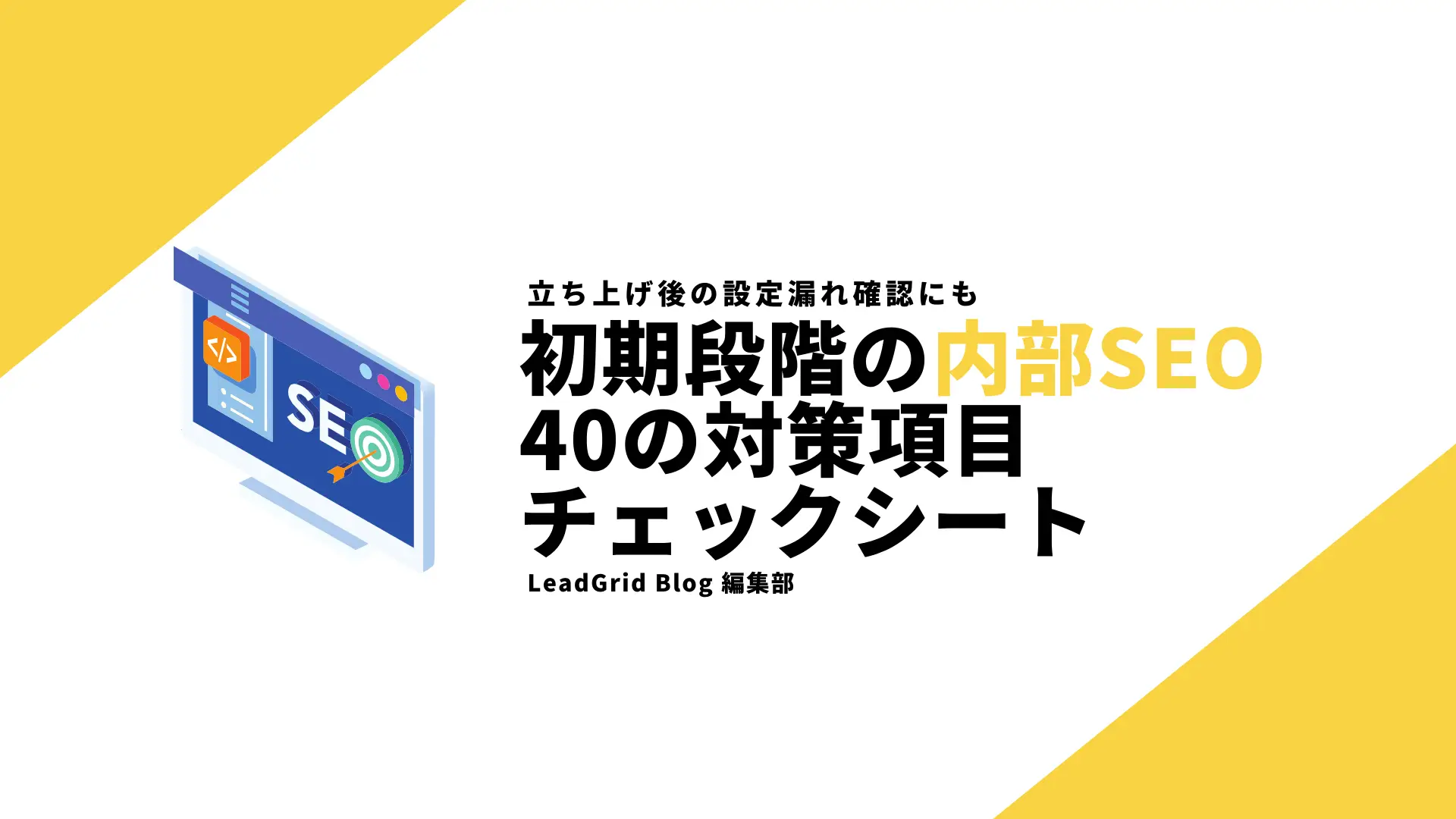
SNS施策(アーンドメディア)や広告施策(ペイドメディア)との掛け合わせでより成果を創出できる
オウンドメディアは、SNS施策(アーンドメディア)や広告施策(ペイドメディア)との掛け合わせでより成果を創出できます。
とくに近年はSNSの検索機能を利用するユーザーも少なくありません。コンテンツをSNSで紹介すれば、SNSからの流入やフォロワーによる拡散が期待できるでしょう。
またホワイトペーパーを公開と同時にPRを打つ、ホワイトペーパーを一括ダウンロードサイトなどにおいてもらうなどすることで、自社やメディアを知ってもらう機会が増えます。
このようにオウンドメディアとSNS、Web広告をうまく組み合わせれば、さまざまな層へのアプローチが可能となるのです。
コンテンツが資産になる
検索エンジンで上位表示を獲得できるコンテンツは資産と同じです。
インターネット広告は出稿を停止すれば流入は途絶えてしまいます。SNSでどれだけヒットした投稿も、投稿して1週間も経つと流入は少なくなるでしょう。
対して検索エンジンの上位表示は、トレンドの変化がない限り新規ユーザーの流入経路として存続し続けます。また一度公開したホワイトペーパーなどの資料は、非公開にするまでは自動のリード獲得装置として機能し続けます。
コンテンツを出し続けることで、流入やリード獲得につながる資産が増え続けるのがオウンドメディアの強みです。
コンテンツを二次利用できる
オウンドメディアで制作したコンテンツは何度でも二次利用できます。
記事を台本として動画を作成する
メールマガジンへ書き直す
要約してSNS投稿に使用する
二次利用した媒体にオウンドメディアの紹介もつければ、様々な媒体のユーザーにアプローチができ取りこぼしが減るので、さらに効果が狙えます。
オウンドメディアを運用する3つのデメリット
企業にとってメリットの多いオウンドメディアですが、デメリットもあります。
成果が出るまで時間がかかる
継続的な運用が難しい
外注を活用する場合、コストがかさむ
成果が出るまで時間がかかる
費用をかけてオウンドメディアを制作しても成果がすぐに出るとは限りません。
なぜなら検索エンジンにオウンドメディアが評価されるには時間がかかるためです。とくに新規サイトの場合、検索順位がつくのに最短でも3カ月〜6カ月、多くのメディアでは年単位の時間を要します。
立ち上がりに時間がかかることを理解し、初期からPVを集めたい場合はペイドメディアとアーンドメディアの併用がおすすめです。
継続的な運用が難しい
オウンドメディアのデメリットとして、継続的な運用が難しいことも挙げられます。
オウンドメディアは中長期的な運用が必要不可欠。継続的に運用するためには専任チームを組むといった社内体制や運用ノウハウが求められますが、社内リソースが枯渇し手が回らなくなってしまうケースが多く見られます。
担当者を専任にする、外注を活用するなどして、無理なく継続的に運用できる方法を探りましょう。
外注を活用する場合、コストがかさむ
オウンドメディア運用では、コンテンツ制作を外注する企業も多く存在します。しかし、外注を活用する場合、コストがかさんでしまうデメリットも。
社内のリソースが足りない、ノウハウがないなどで外部委託する場合、施策を継続する限り費用がかかり続けてしまいます。広告費を削減するためにオウンドメディアに力を入れていても、外注費の負担が大きければ受けられる恩恵も薄くなってしまいます。
ノウハウが蓄積されていない立ち上げ当初は、外注を活用することは悪い選択ではないものの、最終的にはインハウス化を視野に入れて運用することがコスト削減の近道となるでしょう。
オウンドメディア運用のインハウス化を目指したい方は、ぜひ無料配布資料「オウンドメディア運用インハウス化マニュアル」を参考にしてみてください。社内でどのような体制にすべきか、実際にメディアの運用が始まった場合にどのような業務フローになるかなどを解説しております。下記より無料でダウンロードできます。
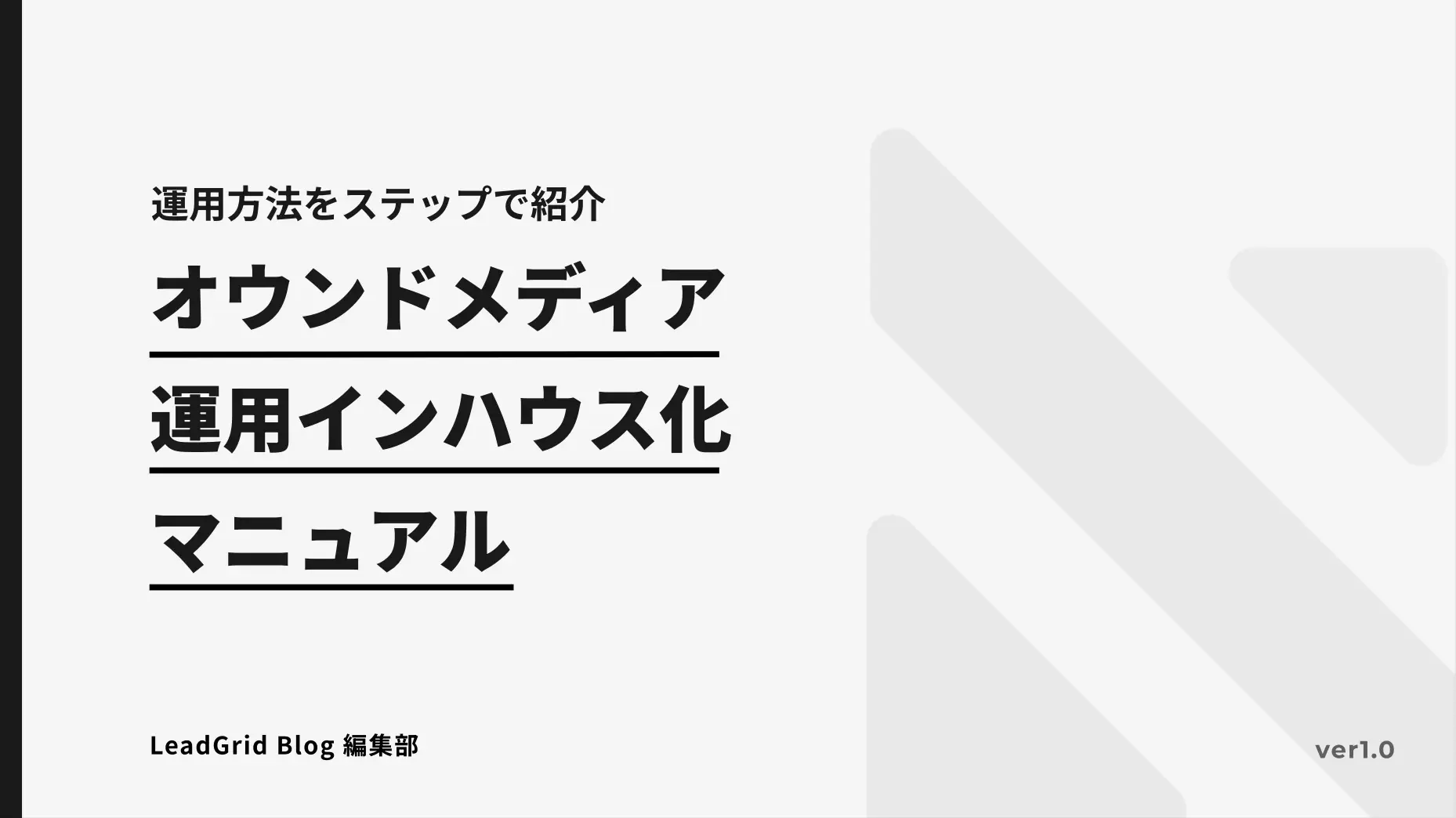
成果が出るオウンドメディア運用の実践フロー6ステップ
実際にオウンドメディアを運用する際は、次の6ステップに従って行いましょう。
- 戦略の立案
- コンテンツ設計
- サイトの構築
- コンテンツ作成
- リリース・運用開始
- ツールを活用した効果測定
1. 戦略の立案
先述のようにオウンドメディアの運用目的は、認知度拡大やブランディング、採用強化などさまざまです。まずは運用目的を達するための戦略を立案しましょう。具体的には目指すべき目標(KGI)や、その中間目標(KPI)を設定し、KPIに向けて戦略を練る形になります。
たとえば目的が自社商品の販売促進であれば、KGIは「1ヶ月のCV数100件」といった具体的な数字になります。その際のKPIの例は以下が考えられます。
- 2年半以内にCV数を100件/月にする
- 2年以内にリードの獲得数を500回/月にする
- 1年半以内にサイトのSSを5万回/月にする
- 1年以内に最低限必要なコンテンツ量(100記事)を確保する
- 半年以内にコンテンツの公開頻度を10記事/月を維持できる体制を整える
このように目標から逆算してKPIを決定し、そのKPIを達成するための戦略を考える必要があります。
たとえば「半年以内にコンテンツの公開頻度を10記事/月を維持できる体制を整える」のKPIについてであれば、まずは運用体制の設計が必要です。コンテンツは「内製する」か「外注する」か、社内の編集者はどこまで兼任するか、などが戦略部分で考えるべきポイントとなります。
2. コンテンツ設計
次に「メディアの目的を達成するためにどんなページが必要か」について考えるコンテンツ設計を行います。
たとえばBtoB企業のオウンドメディアでのKGIが「月あたりのCV数」であった場合は、リード獲得につながるコンテンツ設計を行う必要があります。
この場合サイトの軸となる「検討確度が高く」「月間の検索数が少なくない(ジャンル内)」といったキーワードを主要キーワードに据えて、このキーワードで検索流入を獲得できるように設計を進めていきます。
このとき必要に応じて、商品のペルソナを設定しましょう。ペルソナを設定しておくと詳細なターゲットが明確に定まり、プッシュすべき情報や商品、ユーザーの動向までが現実的に見えてきます。
コンテンツ制作のフェーズにおける方向性のブレが生じにくくなることも、ペルソナを設定するメリットの一つです。
ペルソナは社内で考えるのではなく、実際の顧客にヒアリングするのがおすすめ。現状商品やサービスを利用しているユーザーに直接聞くことで、よりペルソナの具体化が図れます。
ペルソナとターゲットの違いや設計のフローなど、ペルソナ設定に必要な基礎を学びたい方は無料配布資料「ペルソナ設計入門ガイド」をご活用ください。実際にクライアントに対して提供しているペルソナ設計のワークショップの手法を公開しております。下記より無料でダウンロードできます。
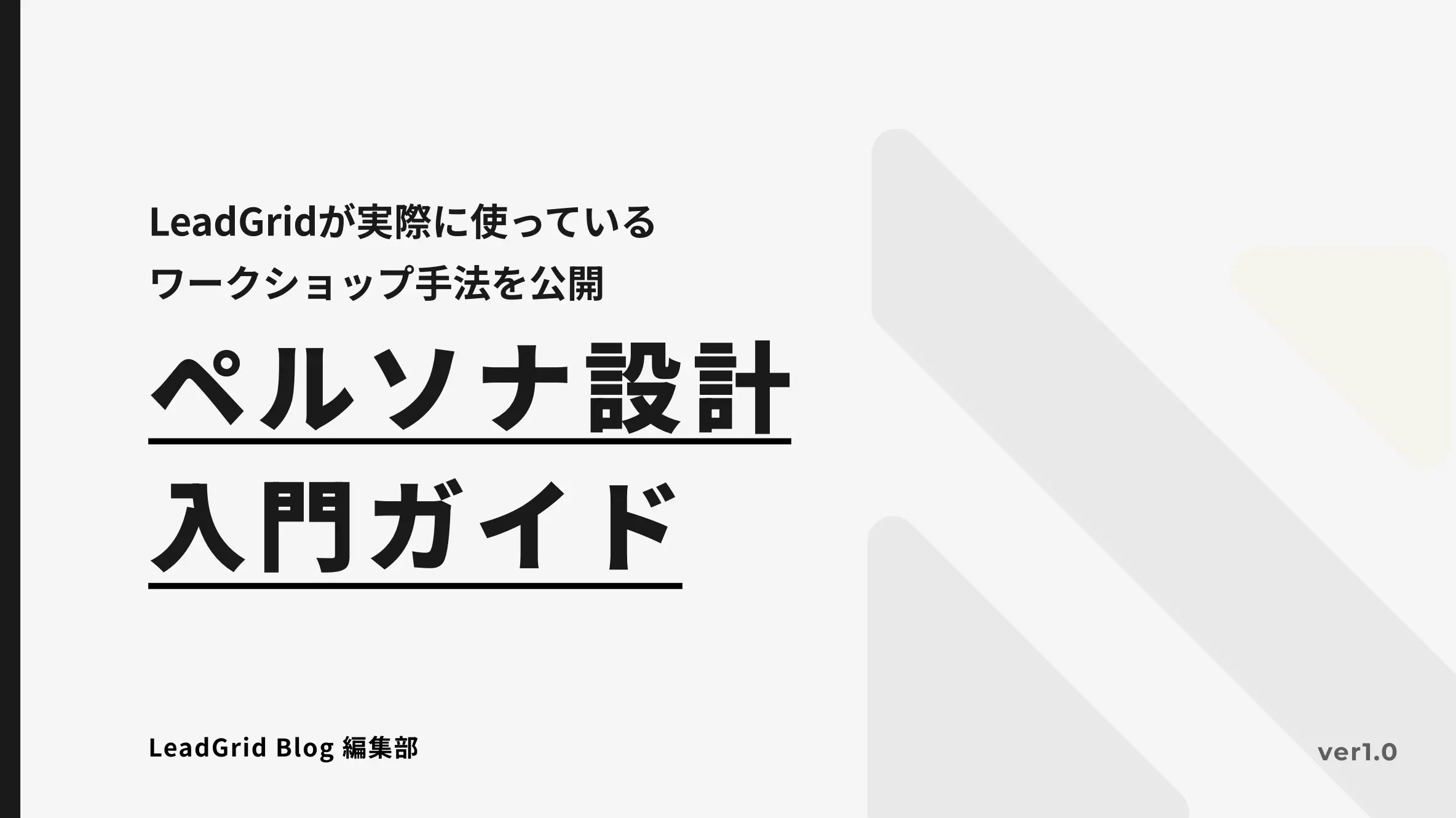
3. サイトの構築
ここまで来たら、いよいよサイトの構築です。
まずはメディア名を決定します。紹介する商品やサービスを連想しやすい、わかりやすいメディア名がおすすめです。このとき商標権の侵害になっていないか、念のため確認しましょう。
参考:特許情報プラットフォーム
メディア名を決めたら、ドメインを決めます。ドメインとは「https://〇〇.com」の〇〇の部分です。ドメインは長すぎす、メディア名に近いものがおすすめです。また既にメインのサイトがある場合は、サブディレクトリでのメディア構築がおすすめです。
関連記事:ドメインの選び方とは?決められない場合のポイントも紹介
またオウンドメディアを制作する方法は大きく2パターンあります。
- サイト作成サービスを利用する
- Web制作会社に依頼する
メディア制作の詳細は「オウンドメディア制作の方法2つと成功させるコツを紹介」をご確認ください。
4. コンテンツ作成
サイトの構築と並行して、コンテンツの作成も進めていきましょう。コンテンツ設計の部分で考えたキーワードについて、検索者の問題が解決できるような記事を作成していくパートです。
コンテンツ設計時に決めたペルソナを記事ターゲットとして、ペルソナの困りごとを解決できるよう網羅性と信頼性を重視した記事を作成しましょう。
網羅性が高く、検索者のニーズを満たす記事を作成するためには記事構成の準備がカギを握ります。SEO記事構成案 穴埋めシートを活用して必要事項の調査と記入を行うことで、SEO評価につながる記事構成が完成するため初めての記事作成でも安心です。

さらに、完成したコンテンツの質をチェックする必要があります。しっかりとクオリティ担保ができる人材を担当者として据えるのが一番効率的でしょう。
「何を基準にしてクオリティ担保すればいいか分からない……」という方のために、LeadGridでは「メディア担当者向け記事クオリティチェックリスト」をご用意しております。
ぜひ、参考にしながら自社コンテンツの品質維持に必要な要素を見つけてみてください。

5. リリース・運用開始
サイトが完成し、ある程度のコンテンツが入稿完了すると、いよいよリリースです。
リリース後は運用の開始です。オウンドメディアは次のように複数名で運用していきます。
- 事業責任者:メディア全体の計画立案、予実管理、予算管理など
- マーケター:効果測定や課題の抽出、改善案の作成など
- 編集者:コンテンツの品質管理
- 制作者:コンテンツ制作
予算や運用規模を見て、運用体制を整備しましょう。
立ち上げの時期は多くのコンテンツが必要になるため、ディレクターやライター層を厚めにすると良いでしょう。なお上記のポジションは兼任することも多々あります(マーケター兼編集者など)
また必要に応じて、外注化もおすすめです。外注化は効率化へとつながります。完全外注や部分外注など、外注もさまざまですので、自社の状況に応じて活用しましょう。
関連記事:オウンドメディア運用代行を利用すべき?おすすめのサービスを紹介
6. ツールを活用した効果測定
記事を公開して一定期間が経過したら、ツールを使って分析を行います。よく利用されるツールは、Google AnalyticsやGoogle Search Console、ヒートマップツールです。
効果測定として確認すべき項目は、アクセスユーザーや流入キーワード、滞在時間などです。商品やサービスを紹介しているページの場合は、ページのどのあたりがよく見られているのかなどのユーザーの行動も確認しましょう。
それぞれの項目について確認すべきことは、アクセスユーザーとペルソナのギャップ、流入キーワードと選定キーワードのズレ、滞在時間が極端に少なくないかです。これらを確認して問題がある場合は、適宜リライトを行いましょう。
関連記事:すぐ使えるWebマーケティングツール17選!目的・課題別に紹介
目的別に見るオウンドメディア成功事例4選
既に成功したオウンドメディアの事例から、設計を学ぶことも重要です。今回はオウンドメディアの目的ごとに、成功した事例を4つ紹介します。
- 【認知拡大】株式会社BAKE|THE BAKE MAGAZINE
- 【リードナーチャリング】SO Technologies株式会社|LISKUL
- 【採用】株式会社メルカリ|メルカン
- 【ブランディング】株式会社クラシコム|北欧、暮らしの道具店
1. 【認知拡大】株式会社BAKE|THE BAKE MAGAZINE
 ▲出典:THE BAKE MAGAZINE
▲出典:THE BAKE MAGAZINE
株式会社BAKEが運営している「THE BAKE MAGAZINE」は、「おいしいは、しあわせにBAKE(バケ)る。そこには、ストーリーがある。」をコンセプトに発信をしているメディアです。お菓子の情報以外にも、つくる人、材料にフォーカスしたコンテンツ制作をしています。
オウンドメディアを立ち上げる前、BAKEは認知度の低さが課題でした。そのため自社商品の思い入れや社内の出来事、さらには他社のお菓子の情報まで発信をして、潜在顧客にまでリーチできるように工夫しました。
結果として、菓子業界で情報を発信するメディアとして注目され、幅広い層の集客に成功しました。数値としても、月間平均7万PV以上を獲得するメディアに成長し、認知度の強化や採用の強化へとつながりました。
2. 【リードナーチャリング】SO Technologies株式会社|LISKUL
 ▲出典:LISKUL
▲出典:LISKUL
SO Technologies株式会社が運営している「LISKUL」は、「日本のすみずみまでWebマーケティングの力を」をコンセプトに運営されているオウンドメディアです。
LISKULは中小企業やベンチャー企業へ、Webマーケティングの知識を届けている会社です。Instagramの運用方法や動画マーケティングなど、最先端のマーケティングについて発信をしています。
同社の課題は、リード獲得数の低さと自社サービスの利用者が少ないことでした。そこで取り組んだことが、今まで蓄積してきたWebマーケティング情報の無料提供です。質の高いWebマーケティング情報をホワイトペーパーという形で提供することにより、リード獲得を目指しました。
その結果、月間PV数は80万PVに達し、1ヶ月の資料ダウンロード数は1,000件以上を突破しました。
参考:LISKUL
3. 【採用】株式会社メルカリ|メルカン
 ▲出典:メルカン
▲出典:メルカン
株式会社メルカリが運営する「メルカン」は、「メルカリの人を伝える」をコンセプトに運営されているオウンドメディアです。メルカンは、メルカリメンバー全員が発信できる点が特徴です。
同社の課題は、採用後のミスマッチでした。メディア等により注目を受けていた一方で、自社が求める人材を上手に伝えられていない点が問題でした。
そのためメルカンでは、社員インタビューやオフィスの紹介、会社内行事を伝えることに重点を置きました。また社員のバックグラウンドや社内の活躍を記事内に書くことで、どういった人材が働いているか、一目でわかるような工夫も施されました。
結果的にメルカンは月間平均3万PV以上を獲得するようになり、入社後のミスマッチを減らすだけではなく、採用エントリー数の増加にもつながりました。
参考:メルカン
4. 【ブランディング】株式会社クラシコム|北欧、暮らしの道具店
 ▲出典:北欧、暮らしの道具店
▲出典:北欧、暮らしの道具店
ブランディングとして成功させた代表例が、株式会社クラシコムが運営している「北欧、暮らしの道具店」です。
こちらのサイトは、メディアとECサイトが合わさったものです。 サイト内では、「読みもの」と「お買いもの」に記事が分かれており、商品の紹介だけではなく、暮らしにフォーカスした記事も多数投稿されています。
同社の課題は、集客でした。購買するユーザーが少ないにも関わらず、広告費が売上の15%を占めていたため、利益率が著しく低い状態でした。そこで広告の出稿ではなく、自社のメディアで集客をすることにより、利益率の改善とともにブランディングを目指しました。
サイトの方針としても、買い物をする気がない人もターゲットにして、読者が読みたいコンテンツを充実させるようにしました。その結果、月間最大1,600万PVを獲得し、売上高も35億円を達成することができました。
参考:北欧、暮らしの道具店
このように、オウンドメディアを成功させた事例を知ることで、自社メディアのヒントを得ることができます。また、成功ポイントを踏まえた上で「オウンドメディアが失敗する5つの原因とその対処法」を活用して、失敗の原因を理解すると、より多角的な戦略作りに役立つでしょう。

オウンドメディア運用で押さえておきたい5つのポイント
オウンドメディアはリリースしてからがスタートです。運用で失敗しないために、3つのコツを押さえておきましょう。
目的を明確にする
体制づくりを優先する
リードナーチャリングも合わせて行う
見かけの数値だけに囚われない
常にユーザーファーストで考える
目的を明確にする
何を目的にオウンドメディアを運営するのか明確にし、運営に関わるメンバーと認識を一致させましょう。
目的が不明瞭なまま運営を続けると、制作するコンテンツに一貫性がなくなり、オウンドメディアとしての個性が出せません。
結果として成果を上げられずに撤退となってしまいます。
体制づくりを優先する
オウンドメディアを長期間安定して運営するためには、体制づくりが必要不可欠です。
例えば1つのコンテンツ(記事)を作るにしても、「企画・構成」「執筆・画像作成」「編集・入稿」「効果測定」と多くの作業が必要です。一部の担当者が企画からすべてを担う体制では、コンテンツのクオリティ維持は難しいでしょう。
そこで、オウンドメディア運用では専任チームを組みましょう。具体的には、「メディア責任者」「ディレクター」「ライター」「Webデザイナー」などが必要になります。
オウンドメディアの規模感や運用フェーズによって、必要な人数は変わってきます。たとえば運用の初期では、大量のコンテンツが必要になるため、ライターを厚めにする傾向があります。社内だけの完結が難しいのであれば、外部委託も有効な手段です。
また専任チームにあわせて、予算も組みましょう。社内で完結させるのか、社外にも頼るかで、予算の規模感は異なります。
オウンドメディアを立ち上げる前に予算を決めておけば、実行体制やフローを決めやすくなります。また運用を開始してからも、残りの予算と相談しながら施策を進められるため、円滑に運営が可能です。
関連記事:オウンドメディア運用代行を利用すべき?おすすめのサービスを紹介
リードナーチャリングも合わせて行う
オウンドメディアで獲得したリード(見込み客)をナーチャリング(育成)し、受注へつなげる施策も重要です。
とくにBtoBの場合、オウンドメディアを閲覧した担当者がその場で商品やサービスの購入を決定することはほぼありません。社内で競合他社との製品と比較検討され、優位性があると判断されてはじめて受注となります。
そのためには、メールマガジンやセミナーを通じて検討プロセスに応じた適切な情報提供が重要。リード獲得後まで見据えたメディア運営が、最終的な成果につながります。
リード獲得を効率的に行うためには全体像を捉えることがポイントです。「リード獲得ロードマップ」では、全体像を3ステップで分かりやすく解説しています。

4. 見かけの数値だけに囚われない
見かけだけの数値に囚われることは、オウンドメディア運用が失敗する要因のひとつです。
オウンドメディアの運用目的は、月間PV数を達成することや、アクセス数を大幅に伸ばすことではありません。
最終的には、自社商品やサービスの売上を伸ばしたり、人材を採用したり、ブランドの認知拡大を図ったりすることなどが目的です。
PVやセッションなどのアクセス数は、これらの目的を達成する指標の1つに過ぎません。
そのため、目的を達成するためにどのような指標を立てていくべきかを設計することが大切です。
5. 常にユーザーファーストで考える
オウンドメディアのコンテンツを作成する際は、伝えたいことだけを書くだけでは成果につながりません。自社のターゲットとなるユーザーがどのような情報を求めているのかを検討したうえで、コンテンツを作成する必要があります。
ユーザーが記事にアクセスしてPV数を獲得していても、ユーザーにとって有益でなければ次のアクションにはつながらず、最終的な目標も達成できないでしょう。
そのため、常にユーザーが求めるコンテンツをユーザー視点で作り、オウンドメディアを運用することが何より重要です。
オウンドメディア成功にはSEOの知識が必要不可欠
オウンドメディアを成功させるには、コンテンツSEOの知識が必要不可欠です。
とくに重要視すべきなのは、以下の3つがあります。
キーワード選定
コンテンツごとのゴール設定
コンテンツの改修・運用
それぞれ順に見ていきましょう。
キーワード選定
オウンドメディアの成功において、キーワード選定は重要な要素のひとつです。自社のターゲットに合わせて適切な対策キーワードを選び、最適化したコンテンツを作成することによって、検索エンジンでの表示順位を向上させることができます。
まず、自社のサービスや製品に関連するキーワードをリサーチしましょう。競争が激しい一般的なキーワードだけでなく、ロングテールキーワードやニッチなキーワードも含めてバランスよく選定することが大切です。
自社ターゲットとなるユーザーの検索意図やニーズに合致するキーワードを把握し、コンテンツを企画しましょう。
コンテンツごとのゴール設定
成功するオウンドメディアを構築するためには、コンテンツごとに明確なゴールを設定することが必要です。
例えば、潜在顧客の興味関心を引きつけてブランド認知を高めたり、商品の販売促進を目指すコンテンツを作成したりと、目的に合わせてゴールを設定しましょう。
あらかじめ明確な目標が定まっていれば、コンテンツ制作の方向性が明確化され、成果を測定しやすくなります。
また、設定したゴールにもとづいてコンテンツを改善することで、オウンドメディアの成果を最大化することが可能です。
コンテンツの改修・運用
オウンドメディアを成功させるためには、コンテンツの改修と効果的な運用が重要です。
定期的な分析を行い、どのコンテンツが効果的であるかを評価しましょう。
また、SEOの観点からコンテンツを最適化し、新しい情報やトレンドに合わせてリライトや更新を行うことも必要不可欠です。
適切なタイミングでコンテンツを更新することで、検索エンジンの評価を高め、読者の興味を持続させることができます。
オウンドメディア運用では常に改善や運用を繰り返すことが大切です。
オウンドメディアはユーザーファーストで進めよう
ターゲット層の求めるコンテンツを分析し、その期待に応える質の高い情報提供を継続することでオウンドメディアは成長していきます。 オウンドメディア成功の鍵は、徹底したユーザーファーストともいえるでしょう。
最終的な目標である商品・サービスの成約をめざす際も、各コンテンツの内容に沿った自然な形で商品紹介や資料請求を挿入する必要があります。
とはいえ担当者さまの手でWebサイトにフォームや資料ダウンロード機能をつけようとすると、かなりの手間と時間がかかってしまいます。そこでおすすめなのが、マーケティングに強みをもつCMSの導入です。

LeadGridなら、コンテンツ別のフォーム設置や資料DL機能など、従来型のCMSでは対応しづらいリード獲得施策〜ナーチャリングまで展開可能。ページを見たまま編集できる「ページ管理機能」や、ドラッグ&ドロップで簡単にフォームを作成できる「フォーム管理機能」が用意されており、Webサイト運営の知識がない方でも簡単に操作できます。
特徴 |
|
料金プラン |
|
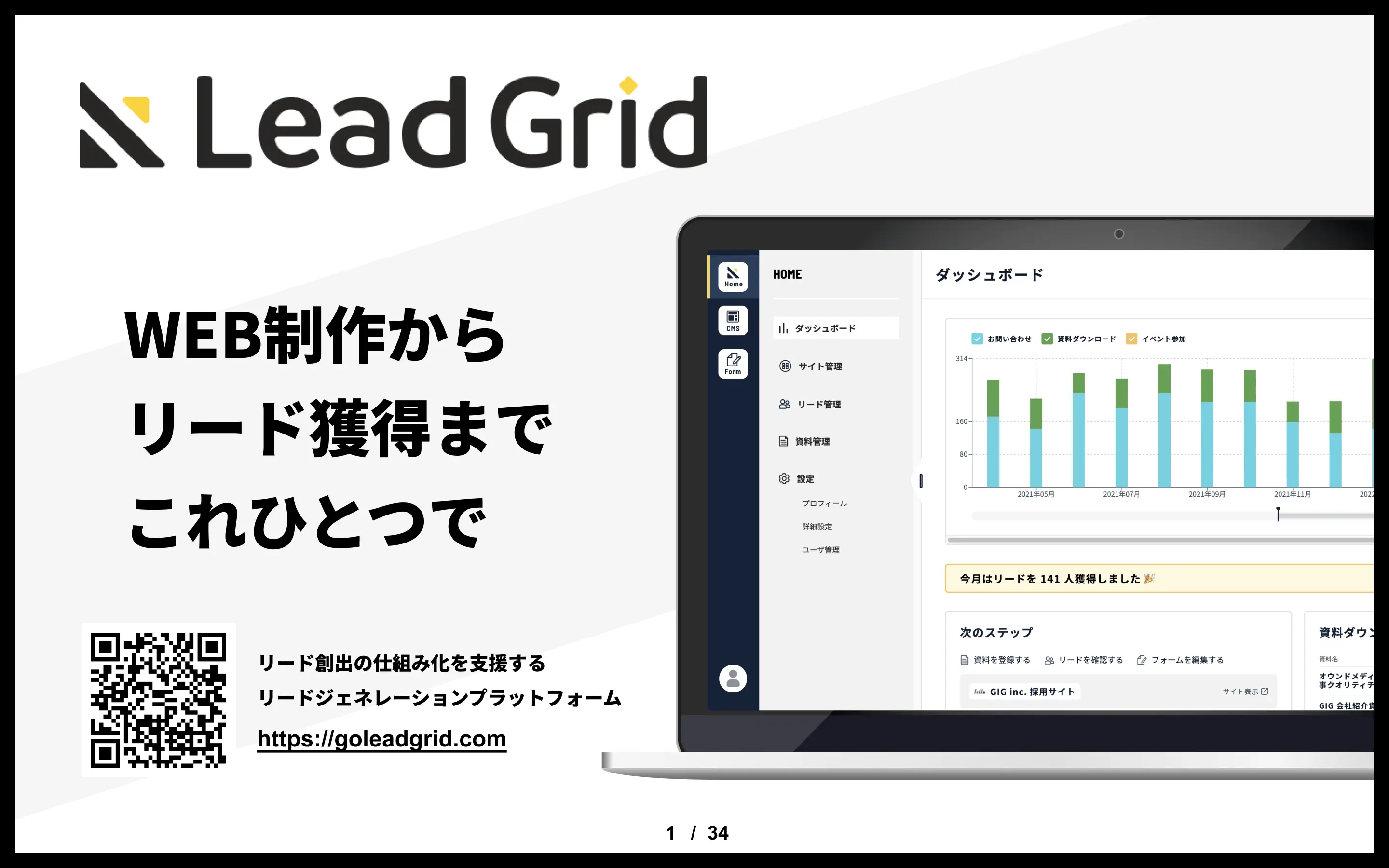
なお、LeadGridで制作したオウンドメディアを予算別にまとめた無料配布資料「予算別オウンドメディア制作事例集」もご用意しております。
ぜひ下記よりダウンロードし、貴社の予算感で具体的にどのようなオウンドメディアを構築できるかイメージするのにお役立てください。
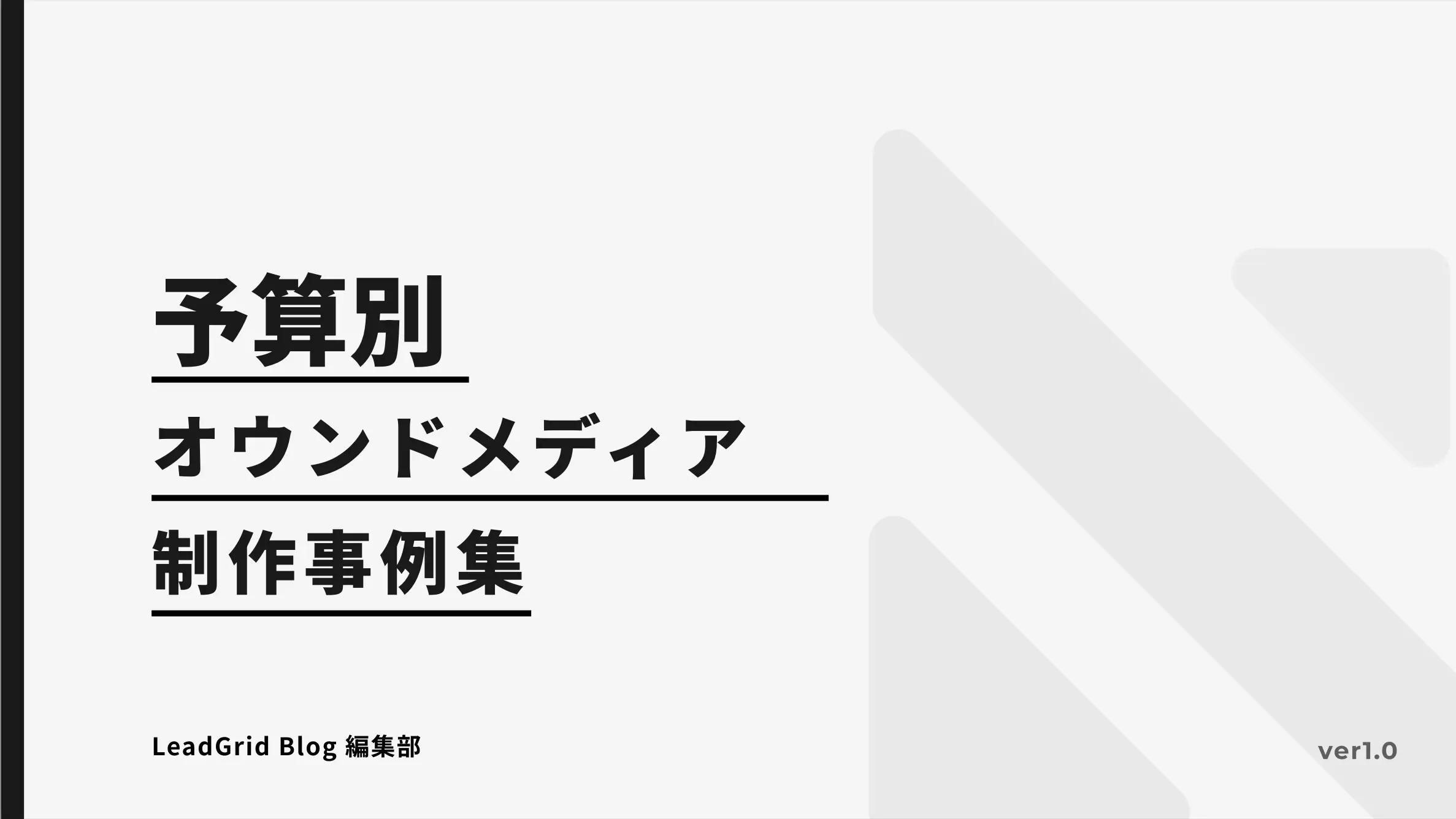
「すぐにでも課題解決のためのオウンドメディアを立ち上げたい……!」と、お考えな方へご紹介したいのが、LeadGridの「最短1週間 15万円〜でメディアを立ち上げられるプラン」です。
コスト・質・スピードを兼ね備えたプランで、予算15万円から最短1週間でメディアの制作〜公開ができます。また、顧客管理機能や資料ダウンロード機能、MAツール連携機能を備えているため、「リードを集める・貯める・分析する」の流れをワンストップで支援できるのも特徴です。
詳細については、気軽にお問い合わせください。

予算別でわかる!
オウンドメディア制作事例集、無料配布中!
各企業の予算に応じた制作事例を一挙公開。オウンドメディア依頼前に費用相場を把握し、自社に最適なサイトを構築するためのアイデアやヒントが満載の資料を無料でダウンロードできます。ぜひご活用ください!
LeadGrid BLOG編集部は、Web制作とデジタルマーケティングの最前線で活躍するプロフェッショナル集団です。Webの専門知識がない企業の担当者にも分かりやすく、実践的な情報を発信いたします。
関連記事
-

ホームページの問い合わせを増やすには?フォームの作り方から改善策まで解説
- # Webマーケティング
- # Webサイト
-

Web集客が得意な代行会社7選|選び方やメリット・デメリットを紹介
- # Webマーケティング
-
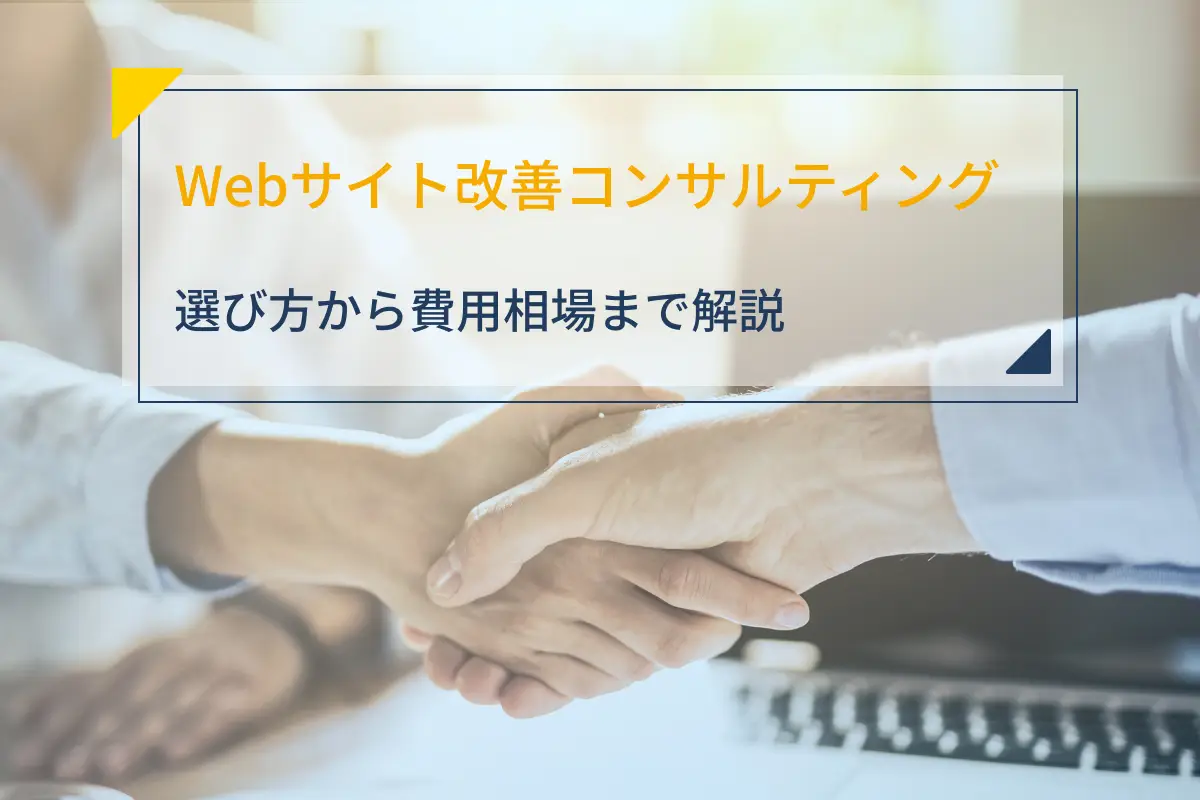
Webサイト改善コンサルティング10選!選び方から費用相場まで解説
- # Webマーケティング
- # Webサイト
-

SNS運用代行とは?依頼できる内容やメリット・おすすめの会社を紹介
- # Webマーケティング
-

TikTok採用とは?メリット・デメリットや成功事例を詳しく解説
- # 採用サイト
-

【比較表付き】MAツールおすすめ13選!選び方や主な機能についても解説
- # Webマーケティング
- # MAツール
Interview
お客様の声
-
SEO・更新性・訴求力の課題を同時に解決するため、リブランディングとCMS導入でサービスサイトを刷新した事例
ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社 様
- # サービスサイト
- # 問い合わせ増加
- # 更新性向上
 Check
Check -
「SEOに閉じないグロースパートナー」へ想起転換したコーポレートサイト刷新の事例
株式会社LANY 様
- # コーポレートサイト
- # リブランディング
- # 採用強化
 Check
Check -
企業のバリューを体現するデザインとCMS刷新で情報発信基盤を強化。期待を超えるサイト構築を実現した事例
株式会社エスネットワークス 様
- # コーポレートサイト
- # 更新性向上
 Check
Check -
採用力強化を目的に更新性の高いCMSを導入し、自社で自由に情報発信できる体制を実現した事例
株式会社ボルテックス 様
- # 採用サイト
- # 採用強化
- # 更新性向上
 Check
Check
Works